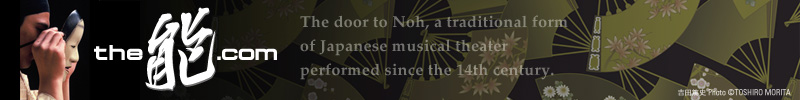
 Trivia
Trivia
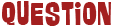


 夏目漱石は能の愛好家だった?(2013年7月19日追加)
夏目漱石は能の愛好家だった?(2013年7月19日追加)

夏目漱石の名作「我輩は猫である」に、主人公の猫が主人の苦紗弥先生の性癖について語るくだりがありますが、そこに引き合いに出されているのは、謡のエピソード。後架(トイレ)で大声を出して謡をうたい、近所で「後架先生」とあだ名をつけられても一考に平気。熊野の一節、「これは平の宗盛なり」というところを「これは平の宗盛にて候」と、間違いを繰り返し、失笑をかっている、と皮肉っています。また「草枕」にも、この旅を能に見立ててみたらどうだろうと思う場面や、「七騎落」「墨田川」「高砂」といった具体的な能に関する記述が見られます。
漱石は、熊本の五高に赴任当時、教授たちの間で盛んに謡われていた宝生流の謡に親しみ始めました。「後架先生」のエピソードも、その頃の実体験をもとにしています。その後、英国留学などによる中断を経て、高浜虚子の紹介でワキ方下懸(下掛)宝生流の家元・宝生新に謡を習うようになりました。妻の鏡子によると、漱石は謡を好み、よく謡っていたということです。有志の稽古会にもしばしば顔を出して謡っていました。
漱石の謡はどういうものだったのでしょうか。周辺を探りますと、寺田寅彦には「先生の謡は巻舌だと言ったら、ひどいことを言うといつまでも覚えていた」、野上豊一郎には「上手とはいえないが、下手とも言えず、個性的であった」、野上弥生子には「ヤギの鳴くような甘ったるい間のびした謡で及第点は上げられない」、安倍能成には「節扱いなど器用だったが放胆であまり拘泥しない謡い振りだった」、師匠の宝生新には「面白いのは謹厳な人格者の漱石先生の謡が、非常に色気のあったところだ」と評価されています。
作品「永日小品」中の「元日」には、弟子たちが新年のあいさつに訪れた際、漱石は、高浜虚子の鼓で謡をうたうことになり、初めて鼓と相対峙したためドギマギしてしまった、という話が興味深く綴られています。明治の文化人には、能は大変身近なものだったことが窺えます。
*「永日小品」並びに漱石の作品の多くは、青空文庫にて読むことができます。
*【2015年1月30日追記】イラストは小鼓ですが、「永日小品」に「…鼓がくると、台所から七輪を持って来さして、かんかんいう炭火の上で鼓の皮を焙(あぶ)り始めた。」とあるため、虚子が持ってきたのは大鼓だと考えられます。なぜこの叙述で大鼓と思われるかは、トリビアNo.70をご参照ください。
- Question 164能を元にしたイタリアオペラとは?
- Question 163幻の流派、“春藤流”が残る地域とは?
- Question 162能面にはモデルがいた?
- Question 161能面は何種類あるの?
- Question 160日本最多の演能記録?
- Question 159慣用句「いざ鎌倉」はお能から生まれた?
- Question 158改元の時だけに演じられる「大典」とは?
- Question 157本物の楽器が登場する曲は?
- Question 156“謡宝生”と呼ばれるのはなぜ?
- Question 155“面打ち”を多く輩出した地は?
- Question 154観阿弥・世阿弥のライバルは?
- Question 153能から生まれた言葉は?
- Question 152“能狂い”の失敗談は?
- Question 151ユニークな能舞台は?
- Question 150「唐事」ってなに?
- Question 149江戸城にも能舞台はあった?
- Question 148能って“お稽古事”にできる?
- Question 147能に残る昔の習慣は?
- Question 146ベテランが演じる曲は?
- Question 145「かぶりもの」って何?
- Question 144どうして扇を膝の前に置くの?
- Question 143能楽版の“第九”?
- Question 142初心者の謡におすすめの曲は?
- Question 141能舞台にはふたつの空間がある?
- Question 140能が影響を与えた芸能は?
- Question 139戦に出た能役者がいる?
- Question 138能楽師に資格は必要?
- Question 137どうして“鏡板”って呼ばれるの?
- Question 136能楽の家に生まれて他分野で活躍した人は?
- Question 135流儀ってかえられるの?
- Question 134古地図にある「○○屋敷」って?
- Question 133「鷺流」狂言ってどういうもの?
- Question 132能楽での扇の役割とは?
- Question 131「道成寺」の鐘は実在する?
- Question 130地方で生き残ったオリジナル能って?
- Question 129能舞台の檜は生きている?
- Question 128狂言の子方が演じる「靭猿」とは?
- Question 127謡本を置く「見台」の模様の由来は?
- Question 126長年伝わる装束の手入れはどうしているの?
- Question 125ツレやワキの装束はどのように決められる?
- Question 124扇の絵柄の決まりごととは?
- Question 123夏目漱石は能の愛好家だった?
- Question 122フランスの小咄をもとにした狂言とは?
- Question 121「道成寺」の鐘はどのように吊るす?
- Question 120「弱法師」のハイライトと四天王寺の関係は?
- Question 119幕末の大老・井伊直弼は、能・狂言作家だった?
- Question 118江戸時代の、能役者出身の大名とは?
- Question 117能とゆかりの深い神事舞って?
- Question 116能は、どのように江戸幕府の式楽となったの?
- Question 115能「隅田川」をもとにしたオペラって?
- Question 114能の「小書」の始まりは?
- Question 113能のすり足の源は?
- Question 112泉鏡花は能役者の家の出だった?
- Question 111能の影響がある日本映画とは?
- Question 110仕舞扇の文様は、流儀で決まりがある?
- Question 109奈良の天河神社と能の深い縁とは?
- Question 108江戸時代、寺子屋で教えられた小謡の役割とは?
- Question 107囃子方や地謡の着物は曲で違う?
- Question 106「芝居」という言葉は能から生まれた?
- Question 105逆輸入された能ってあるの?
- Question 104豊臣秀吉が舞った新作能とは?
- Question 103太鼓の名人だった武将とは?
- Question 102戦国時代の能のパトロンは誰?
- Question 101結局、世阿弥は京にもどれたの?
- Question 100大鼓と小鼓は、どんな関係にあるの?
- Question 99能における「発声」の効用とは?
- Question 98「羽衣」が人気なのはなぜ?
- Question 97能は腰痛に効く?
- Question 96若き日の弁慶ってどんな人?
- Question 95「勧進能」って何?
- Question 94能の上演時間は昔から同じなの?
- Question 93能の海外公演はいつ頃からあるの?
- Question 92佐渡島に多くの能舞台があるのはなぜ?
- Question 91後見は、舞台の上以外では何をしているの?
- Question 90能舞台は平らなの?
- Question 89能楽用の足袋って特別なの?
- Question 88能の演者は、オールラウンドプレイヤー?
- Question 87囃子方のソロ演奏の舞台もあるの?
- Question 86素謡鑑賞の面白いところ、ためになるところは?
- Question 85「中入」って休憩時間なの?
- Question 84「道成寺」で小鼓方の特別なやり方とは?
- Question 83「ワキ留め」ってなに?
- Question 82「土蜘蛛」の蜘蛛の巣や糸はどういうふうに使うの?
- Question 81「蝋燭(ろうそく)能」って何?
- Question 80「善知鳥」の舞台はどういうところ?
- Question 79作品の成否にアドリブも関係する?
- Question 78観客が出演者の一部になる演目とは?
- Question 77どうして演者が動かない時間が長いの?
- Question 76揚げ幕の奥から呼びかける声は?
- Question 75演じられる曲数はどのくらいあるの?
- Question 74装束を替えるタイミングはいつも同じ?
- Question 73囃子方のかけ声は何のため?
- Question 72小鼓の基本の音とは?
- Question 71囃子方にいつも太鼓は入っている?
- Question 70大鼓の準備時間はどのくらい?
- Question 69開幕ベルは何度鳴る?
- Question 68能の基音とは?
- Question 67能楽の専門用語「コミ」ってどんな意味?
- Question 66能舞台で最初に観られているのは?
- Question 65能にはどういう者たちが登場するの?
- Question 64笛方は生涯で何本笛を持つ?
- Question 63「小謡」は能理解への近道?
- Question 62能舞台に3つめの出入り口があった?
- Question 61能の演出はいつも同じ?
- Question 60「キザハシ」は何のためにある?
- Question 59能装束の「色入り」ってどういう意味?
- Question 58能楽専門の美術館ってあるの?
- Question 57「がぎぐげご」をどう発声する?
- Question 56橋掛かりの長さは決まっているの?
- Question 55「乱能」ってどういうもの?
- Question 54シテの着付けは誰がするの?
- Question 53浮世絵師の写楽は能役者だった?
- Question 52能の型・所作の基本とは?
- Question 51舞台の「お目付け役」は誰?
- Question 50能の舞台では右、左のどっちが上位?
- Question 49舞台で小鼓方が指をなめるのはなぜ?
- Question 48面をふたつ重ねてかける演目があるって本当?
- Question 47能舞台で使う「道具」にはどんな種類があるの?
- Question 46能役者の心拍数がアスリートなみって本当?
- Question 45大人数の地謡方はどうやって音を合わせる?
- Question 44舞台の上で能役者はメガネをかけられる?
- Question 43能の謡は“声明”の影響を受けている?
- Question 42ワキ方はなぜ能面をつけない?
- Question 41能舞台では、羽織は着ない?
- Question 40能の笛「能管」はほかの笛とどう違う?
- Question 39“能にして能にあらず”と言われる「翁」って?
- Question 38豊臣秀吉は能の“名優”だった?
- Question 37演能のためのリハーサルは何回ある?
- Question 36能舞台の柱はどんなもの?
- Question 35女面に特有の、造形上の技巧とは?
- Question 34揚幕の開閉はどうやるの?
- Question 33世阿弥直筆の本はある?
- Question 32薪能のかがり火は、どうやっておこすの?
- Question 31能舞台のシンボル、鏡板はいつからある?
- Question 30謡本がベストセラーになったのはいつ?
- Question 29雨が降ったら、薪能はどうなる?
- Question 28「袴能」とは?
- Question 27能面の毛の原材料は?
- Question 26人数のいちばん多い演目は?
- Question 25女性も能楽師になれる?
- Question 24能楽師がもつ扇はどう違う?
- Question 23能舞台から落ちることはある?
- Question 22能の装束の重さはどれくらい?
- Question 21国宝に指定された能舞台とは?
- Question 20能では演出家がいない!?
- Question 19地謡には決まったキーはない
- Question 18なぜ「能」というの?
- Question 17能楽堂はいつ、どのように誕生した?
- Question 16揚幕はなぜカラフル?
- Question 15能面はなぜ小さい?
- Question 14“寝てはならぬ”?
- Question 13心がけたい観能のマナーとは?
- Question 12観能のベストポジションは?
- Question 11新作能はいつまで新作?
- Question 10観能に拍手は必要?
- Question 9能楽師はなぜ70代でも現役でいられるの?
- Question 8能面のお手入れはどうするの?
- Question 7能のカツラにはどんな種類があるの?
- Question 6子方(子役)ではどういう役柄が演じられる?
- Question 5“披(ひら)キ”って何?
- Question 4橋がかりは歌舞伎の花道と同じ?
- Question 3床下の甕(かめ)が音響効果をあげる?
- Question 2能と狂言、どっちが古い?
- Question 1足袋の色には決まりがあるの?


