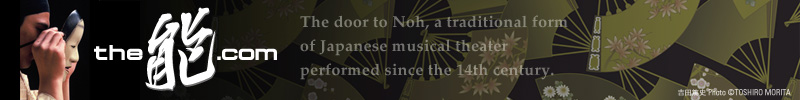
 What is “Kyogen”?
What is “Kyogen”?
本狂言と間狂言の違い
狂言は能と同じく、散楽を源流とする芸能で、古くから能と深く関わってきました。能と大きく違うのは、能でほとんど表現されない「笑い」に結びつく芸能だというところです。散楽はこっけいさが特徴でしたから、狂言は元の姿を受け継いだといえるでしょう。

2009年8月9日 国立能楽堂「第25回 狂言やるまい会 東京公演 〜十二世野村又三郎信廣 三回忌追善〜」より
狂言が芸能として姿を現したといわれる南北朝時代、すでに狂言は能と一緒のプログラムで演じられていたようです。能と深くつながりを保ってきた狂言には、主に能と能の間に、ひとつの劇として演じられる「本狂言」、能一曲のなかで演じられる「
「狂言」ということばの意味
今でこそ「狂言」といえば、この笑劇を指すことばで定着していますが、もともとは違いました。狂言は古い中国のことばで、道理に合わない、常軌を逸したことば、あるいは冗談を指していました。日本では万葉集に「狂言=たわごと」と読まれて出てくるなど、古代からなじみがありました。
その後、唐の白居易が著した白氏文集に記された「狂言綺語(きょうげんきご、きょうげんきぎょ)」が平安時代に編まれた和漢朗詠集に取り入れられ、仏教から見て偽りや虚飾に満ちている、と物語などを非難する場合に使われました。こうして、でたらめな物言いや戯言、尋常でない言葉遣いの意味を持って普及した狂言は、次第に「
笑劇・狂言の成り立ちと推移
奈良時代に中国から入ってきた散楽は、こっけいな芸や物まね、曲芸、奇術などさまざまな大衆芸能の集まりでした。平安時代になると散楽は猿楽と呼ばれるようになり、こっけいさをより際立たせます。ぽっと出の田舎者が都で右往左往する様子などを演じて笑いを取るといった芸が主流でした。これを母胎に、能は歌舞や幽玄を取り入れて大きく変わりますが、狂言は本来のこっけい芸を担うこととなります。
狂言の成立は不明な部分も多いのですが、14世紀の中ごろに狂言の役者は「ヲカシ」という名前で歴史の舞台に登場し、世阿弥もまた「ヲカシ」という名で呼び、一座で一緒に興行し、能と狂言が交互に演じられたことを記録しています。
世阿弥の時代には、まだ即興的で俗っぽい下ネタ交じりの芸が勝っていたようですが、徐々に演目も整い洗練度を増しながら、16世紀の後半には現存する最古の狂言台本も生まれます。さまざまな役者グループが交流しつつ流動的に活躍する時代が続いた後、江戸時代になると大蔵流、鷺流のふたつが幕府のお抱えになって勢力を振るう一方、尾張徳川家に仕えて流儀を確立した和泉流が京都、尾張、加賀に勢力をもちます。幕府の式楽になって、狂言も即興的な活力は削がれましたが、その分様式美の追求が進んだとみられます。
明治維新で能とともに狂言も一時大きく衰退し、鷺流に至っては断絶の憂き目に遭います。その後、現在まで続く和泉流、大蔵流の二流は盛り返し、第2次世界大戦後には意欲的な狂言方の努力の成果も出て、狂言はかなりのブームを作ります。狂言だけを演じる「狂言尽くし」の会も、能舞台だけでなく市民ホールなど多様な場で頻繁に行われるようになりました。源流の散楽がそうであったように、身近な大衆芸能として、パワーを発揮しています。
狂言の表現

2008年10月25日 セルリアンタワー能楽堂「第24回 狂言やるまい会 東京公演」より
狂言は、室町時代の口語をベースにした、おおらかな対話の語りと、時に写実的で時におおげさで類型化したきめ細かいしぐさとで、主に「笑い」を引き出します。世阿弥は狂言の役者に下卑た俗っぽい笑いではなく、楽しい笑いを目指せと説きました。そのことば通り、狂言では、ことばのリズムや動きの面白さ、人物像やストーリーの深さの両面で総合的に笑わせるため、嫌味の少ない品の良さが伴います。
笑いだけではなく、悲哀や同情、懐かしさといったいろんな感情を呼び起こしたり、強烈な風刺があったり、人間の性に迫る哲学的な内容が見られたりするなど、懐の深さも特徴的です。能の様式美とも共通し、田楽や
本狂言の内容と種類
本狂言の演目は、大蔵流、和泉流合わせておよそ260番あります。狂言では実にさまざまな人びと、者共が登場し、生活の中で繰り広げられる物語をベースに、笑いを取る寸劇を構成します。主人のみかんを食べてしまって、あれこれ言い訳する太郎冠者(柑子)、酒飲みの妻に業を煮やした恐妻家の夫(因幡堂)、かわいい小猿を殺されまいと嘆願する猿曳き(靭猿)、嫁がほしいと願をかける男たち(伊文字ほか)、柿を盗み食いする山伏(柿山伏)、物見遊山に出かけた田舎の大名(萩大名)、旅の道中で一緒になった宗派の違う坊主ふたり(宗論)、猟師に眷属を殺されてやめさせようと人に化ける狐(釣狐)、人間に近づいて血を吸おうと相撲取りに扮する蚊の精(蚊相撲)……。各々、それぞれの物語を巧みな語りと、身振り、手振り、そのほかいろいろの動きで面白おかしく表現します。登場するのは大体2〜3名で15分〜20分ほどの短いものが多いのですが、40分以上に及ぶ大作や、十数人以上も出演する大掛かりな演目もあります。
狂言の種類は、主人公として出てくる人物等で大体次のように分かれます。
| 福神狂言 | 福の神が福を授けます |
| 百姓狂言 | 年貢を納める百姓の話 |
| 大名狂言 | 大名が出てくる話 |
| 小名狂言 | 太郎冠者が活躍します |
| 聟(むこ)取狂言 | 結婚をめぐって聟がいろいろ立ち回ります |
| 女狂言 | 気の強い妻など、女性を主人公とするもの |
| 鬼狂言 | 鬼や閻魔大王がユーモラスに登場します |
| 出家狂言 | 僧侶が笑い者になります |
| 山伏狂言 | 中途半端な山伏が出てきます |
| 座頭狂言 | 盲目の人などを主人公とします |
| 舞狂言 | 能の構成に沿ったパロディ的なもの |
| 集狂言 | その他の狂言。動物も出てきます |
間狂言のいろいろ
能の一部をなす間狂言は、物語の進行に欠かせない重要な役割を果たし、主に「語り間」「アシライ間」という形式があります。
「語り間」の代表格が「居語り」です。これは前後半に分かれた夢幻能などで、シテが中入りで引っ込んだ後、物語の場所に住む者などとして登場し、物語のエッセンスやポイントを語るというもの。座って語るので居語りと呼ばれます。物語の内容をわかりやすいことばで話し、能で触れられていないエピソードや背景の解説も入るため、観客の内容理解に役立ち、後半を待ち受ける雰囲気を盛り上げます。また、
「アシライ間」は現在能に多く、シテやワキとも絡みながら物語の進行に大きくかかわります。たとえば「道成寺」では、間狂言はお寺の下働きをする男として登場し、シテの白拍子の求めに応じて寺のなかに引き入れてしまいます。また「黒塚/安達原」では、ワキに何度も止められながらもシテの閨を覗きに行って、鬼女の正体を知って、皆に知らせ、逃げ出します。大きな場面の展開にはアシライ間が関わることが多いのです。また物語の冒頭に出てきて、舞台進行のきっかけを作る「
「三番叟〔三番三〕」を踏む
狂言方で、もうひとつ重要なのが「翁」で勤める「
「三番叟〔三番三〕」はシテ方の翁が退場したあとの後半の主役であり、直面で「揉ノ段」を演じ、その後に黒い翁の面をかけて鈴を持って「鈴ノ段」を演じます。足で踏み込む動きが多く、種を撒くような動作もあります。神になって祝福、祈願の舞を演じきるのです。狂言方では「三番叟〔三番三〕」を踏む、と表現しています。


