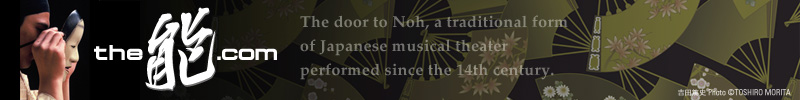
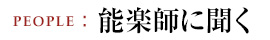 Noh Talk
Noh Talk
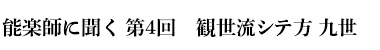
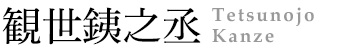


今回より、喜多流能楽師・大島衣恵氏を聞き手に迎えてインタビューをお届けします。
2017年4月初め、青山に九世 観世銕之丞氏を訪ねた。
緊張した面持ちで向かった大島氏を、柔らかな笑顔で観世氏が迎えてくださった。温厚なお人柄が滲む語り口で、時折冗談がこぼれる茶目っ気に緊張もほぐされていく。謡の実演を交えながら、家を継ぐことに対する葛藤や独自の能楽論などをうかがった。
![]() 第1部 葛藤の末、気づいたこと
第1部 葛藤の末、気づいたこと
2017年6月 聞き手:大島衣恵(喜多流能楽師) 写真:大井成義
第1部 葛藤の末、気づいたこと
銕仙会とは
大島 the能ドットコムでは、お能の世界に触れたことの無い方にも、能の魅力やおもしろさを知っていただきたい、という思いがありますので、初心の方へ向けてという視点でもお話を伺いたいと思います。
まず、先生が主宰される銕仙会についてお聞かせいただけますか。
観世 はい。銕仙会ができたのは今から100年近く前です。明治時代にようやくお客さまに対して能をお見せするような会ができはじめ、発会当時(大正の頃)の定期会は、日頃の稽古仲間が集まって演能するものでした。多くの定期会がそうでありますように、最初は稽古会の延長線上で、今のように玄人会・素人会の区別があまりはっきりしていなかったんじゃなかろうかと思います。
うち(観世銕之丞家)は明治維新の頃から梅若家と親戚関係で、一緒に稽古しておりました。『梅若実日記』などにも記載がありますように、ほとんど梅若の一門としてやっていた時期がありました。特に“一六の稽古”と言って、一と六が付く日に稽古能をやっていたんですね。その一六の稽古で五世、六世、七世の銕之丞は育っています。その後、銕之丞家と梅若家が別れてやるようになってからも、稽古能という形で週に1度午前中に稽古する習慣がありました。ですので、いつを発会というのか分かりませんが、ほぼ100年前から始まったのは確かです。
大島 長く続いてこられたんですね。
観世 銕之丞の銕と、親戚でもあり稽古仲間であった笛方の家の出身の一噌銑二(いっそうせんじ)さんという方がおられて、今の仙幸(ひさゆき)さんのご先祖のひとりですけれども、ふたりの名前をとって「銕銑会」という玄人の稽古会を始めたのがはじまりだろうと思っています。また一説には、将軍様から拝領伝来した小さ刀にテッセンの模様がついていて、字を変えて「銕仙会」としたという話もあるんですが、定かではありません。その小さ刀でも残っていれば良いのですが、それも戦災か関東大震災で焼けてしまったんだろうと思います。この舞台は昭和55年までは木造平屋建てでした。
大島 その当時は周囲に謡のお稽古の声なども響いてらしたんでしょうね。
観世 夏に錬成会があって、昔は朝7時からやっていました。窓を完全に開け放していたので、隣から赤ちゃんをおんぶした人が「あんた達は朝から笛や太鼓やらを使って何やっているか知らないけれどなんとかしなさい!」と怒鳴り込んでこられたこともありました(笑)。それからは真夏でも雨戸まで閉めて、時間も少しずらした8時からやるようになったそうです。
大島 それでその後コンクリート建てに?
観世 ええ、だいぶ後のことですけどね。

表参道交差点をみゆき通りに進み、高級ショップなどが軒を連ねる一角に佇む銕仙会能楽研修所外観。1980(昭和55)年、立て替えによりモダンな佇まいとなった。
観世の分家に生まれて
大島 私は学生の頃に銕仙会の青山能や定期能を拝見するようになって、生まれ育った喜多流の能とはまた違う新鮮さを感じさせていただきました。
先生ご自身がお子さんの頃、観世の分家というお家で育たれた中での思いをお聞かせください。
観世 ご存じの通り、幼い頃から仕舞などの稽古をします。子どもの役だけではなく、妖精や神様といった類いもやります。または「船弁慶【→演目事典】」や「安宅【→演目事典】」の義経のように、本来は大人だけど子どもにした方が舞台上の配役のコントラストがいいために子方が務める役があります。
その頃の稽古は完全にアメとムチの世界ですね。一生懸命やってうまくいくと「よくできたね、じゃあこれあげるよ」とご褒美をもらって「ああ嬉しい」と思いながらやるわけです。うまくいかないと「ダメじゃないか!」と頭ごなしに怒られて、「やっぱりお父さん(八世観世銕之丞、本名:観世静夫)は怖い…」とおびえました。本当に怖かったですよ、手もとんできますし、日頃鍛えている声で頭ごなしに怒られるので萎縮するんです。なので、親父が怒号をあげると一瞬くっと居竦むのが晩年の頃まで変わらなかったですね(笑)。
私は親父が一生懸命稽古してくれても、自分から積極的に稽古しようという性質(たち)ではなかったんです。私は男兄弟がなく、姉と妹でしたので競争原理というのがあまり育たなかった。衣恵さんには失礼だけれども、「女の子は辞められていいな」くらいにしか思ってなかったんです。
大島 いえいえ、うちの弟(喜多流シテ方・大島輝久氏)もたぶんそう思っていたと思います。わたしが辞めなかっただけで。
観世 なので非常にのんきにやっておりました。親父は忙しいとあまりしてくれなかったですね。1回稽古した曲だと、「お前やっているから分かっているね」と言われてしまい、「分かりません…」と言うと、「しょうがねぇな」なんて言いながら稽古をつけてくれました。
大島 ええ、分かります。
観世 親父達は男4人兄弟なんです。寿夫、栄夫(ひでお)、それから三男の幸夫(ゆきお)という方がいて、この方が10歳か11歳で亡くなられて、それで親父(静夫)だったんです。親父は末っ子だったからお兄ちゃん達の稽古をよく見ていたんですね。お兄ちゃん達の仲間に入れて欲しいという感じで稽古に参加していたでしょうから、少し習えばある程度のことは分かっちゃう。それもあって親父は子どもの頃から能が好きだったんでしょうけど、僕はそういったものがなくて……。僕の子どもの頃でさえ、すでに生活の中でそんなに正座をしなくても済んでいた時代なので、足が痛くなって動くと、「なんで動くんだ!!」と叱られましたけど、そりゃ痛いですよね。
大島 幼い時は正座だけでもつらいものですよね。
観世 それでも舞台に出てずいぶん子方を務めました。調子がいい時は声がよく出るのですが喉を損じやすかったため、子方が続く時はプレッシャーを感じていました。子どもの頃から親父に怒られたので、手を抜いて謡うことが全然できない。稽古だろうと申し合わせだろうと必死になって声を出す癖があるんです。それは今でもあまり変わらないですね。
舞台で大きな声を出すことで、大人が作ってきた世界観をボンと壊し、状況を一変させてしまうだけの力がある子方は、意味が分からなくてもそれなりに快感でした。ですから、舞台に出ることは怖かったですが魅力的な体験でしたね。
中学生の後半くらいから子方の役はつかなくなり、大人の稽古に切り替わる。大人の曲になり、面も付けるようになると、まったく状況が変わってきました。その頃は親父も働き盛りで、自身の仕事に多くのエネルギーを使うようになり、私も学校のことで時間がとれなくなったため、なかなか稽古の時間がとれなくなりました。
大島 親子ってそうなるんですよね。
葛藤した青春時代
観世 囃子の稽古や地謡、後見につくようになると、とにかく山のように覚えなきゃならないことがあるんですよね。毎回必死になってやるんですけど、学校の勉強もあるし友達の誘いもあるしで……。そうすると結局当日まで覚えられないものがたまる。そんな時に地謡に出ると、後ろの人の声を聞いてなんとなくショボショボと声を出すだけ。みんなはお腹からぐわっと声を出しているのに、こちらは口先だけで音を合わせてしまうので、「調子がはずれてる!」ときつく言われてとっても腐りました。
下働きとして早くに楽屋に行ったり、後片付けもするけれども怒られてばかり。装束を畳んでいても、「畳み方が悪い」と文句しか言われない。友達と遊んだり、学校のクラブに行くのは楽しかったですが、勉強はやってなかったから成績が下がり、補習の勉強にも行かされたりする。囃子の稽古もあるのに、いよいよ時間が足りなくなる……。
その頃は「自分は果たして能をやるべきなのか。全然才能もないし、辞めた方がいいんじゃないか」と毎日頭にありました。片や親父や寿夫の伯父はやっぱりスターですからね。周りの人達が、少女漫画みたく目の中に星をきらきらと輝かせながら話を聞いているんですよね。「上手いな、すごいな」と思って自分で稽古してみるけれど上手くいかず、「なんでこんなに自分が下手なんだろう……」と思い詰めました。上手くいく方法は分からなくても、下手なことは分かるんです。だから理想の舞台と現実との落差というのが大変に苦しくて、一日の大半を「明日親父にどんなに殴られてもいいから辞めるって言おう」と思っていた日々がありました。
大島 ああ、そうだったんですか。
観世 僕の家では僕と従兄弟がやる可能性があったんですけれど、従兄弟の方は辞めてしまいましたから、僕だけしか残っていない。この家は継がなくちゃいけない、という責任はありましたけれど、親父や伯父のような世界には到底近づけるものではない。絶対周りの人も不幸にしてしまうし、自分も不幸になるのだから、成人するくらいまでには辞めようと思っていました。
ところが寿夫の伯父が突然亡くなって状況が変わったんです。銕仙会は人数の少ない集団ですから、トップがひとり欠けると人手が不足するので、とにかく実戦配備。22歳でしたけど、あそこの地謡ね、あそこの後見ね、荷物持ってきて、とどんどん仕事がありました。それと、親父が寿夫の伯父の代役をするんですね。寿夫の伯父の役っていうのは難しい役ばかりでしたし、親父もその時すでにスターでしたから、自分自身の仕事も多く多忙を極めていました。稽古だ申し合わせだと朝早く出て、お舞台が終わったならば必ず飲みに行って、その日の垢を落として午前様になる。それから仮眠をとるけれど、僕が学校に行く時にはもう調べ物も終わって出かけていく。こんな生活していたら親父死ぬな、と思いました。
大島 トップともなると、ご自身のことに加えてお付き合いも大切でしょうから、その激務のほどが想像されます。

能面の虫干し作業風景か。六世 銕之丞の観世華雪。静夫の長兄で、九世観世銕之丞からみると叔父にあたる観世寿夫。九世観世銕之丞の父親で、八世 銕之丞の観世静夫。

父 観世静夫や、叔父 観世寿夫との思い出話では、時折顔をほころばせる場面も。
観世 親父も寿夫の伯父も、書生を引き連れることを嫌っていた時期がありまして単独行動するんです。荷物も自分で持っていたので、とりあえず重い荷物は持っていってあげよう、というか持って行かなきゃと思いました。僕自身に生活能力があるわけではないし、今ここで親父が倒れて、この家の責任が僕にかぶさってきても何もできないから、とにかく親父の寿命を一日でも延ばそうという思いで鞄持ちを始めたんです。すると、普段「何を怒っているんだ? おふくろになんでこんな理不尽なことで怒鳴っているんだ?」と思っていたことが、親父は本当は何をしてもらいたいのか、どういうことがあってこういう言い方になるのかというのが見えてきました。鞄持ちとして親父に付き、人に出会った時に親父がどんな対応しているかによって、親父が言わなくても分かるようになってきたんです。そこで初めて、お舞台に出るまでにさまざまなプロセスや付き合いがあり、支えている人がいるから舞台が滞りなく進行しているんだ、ということが分かるようになりました。
大島 伯父様が亡くなられたのを機に、お父上を支えたいという思いで始められた鞄持ちがお能の舞台裏を見せてくれたんですね。
観世 それから次第に能に対する恐怖心が薄らいで、一生懸命取り組めるようになりました。それまでは舞台に出た上のことだけを考えていて、親父や伯父をいきなり比較対象にしていたんですが、それはダメだったんですね。萎縮しちゃって。自分でいくら稽古していても、「絶対適わない」と思い込んでいました。その発想ではだめなんですけれど、先に出ていたんですね。でも徐々に、「そうじゃない、間違えてもいい、変な声出てもいい、数重ねて稽古するんだ」と切り替わった。そうしたら不思議なもので、周りの目が変わってきたんです。それをあと10年くらい早く気がついていれば、もうちょっとましな能が舞えるんですけれど。
大島 いえいえ、そんなことはありません! けれど、わたくしどものような地方の家でも、やはり男の子は跡継ぎにしないといけないという何かプレッシャーの中で育って、弟も苦しんでいました。それにもまして、観世の分家というお立場もあるし、お父上の世代の周りの活躍ぶりというのも目の当たりにされると、それはやはり計り知れない葛藤がおありだったのでしょうね。

“思っていることを素直に”と心がけて
大島 ご自身が変わられて、周りも変わったということでしたが、芸について核にしておられる心構えなどがありましたらお教えください。
観世 そうですね。あまり決めてかかるわけではなくて、とにかく最初は型付け通り、本通りにやっていきたいなと思っています。ポリシーとしては「素直にやっていく」、でしょうか。それと頭の中にある伯父ですとか親父のイメージでやっていますね。ただそれだけだと思い違いなどもあるんだろうと思うので、先輩に聞いたり、映像に残っているものは映像を見たりもしますけど。それでも映像の通りにはできませんし、思っていることを素直にやっていくということを心がけています。
大島 地謡や囃子方との関係などはいかがでしょう。舞台をひとつのチームで作り上げていく時、地謡を謡う時に心がけていらっしゃることございますか?
観世 やはり地謡はシテよりも難しいですよね。舞われている方のことも考えていかなければならないし、囃子、舞台全体の雰囲気のこともあります。シテは、任せたいというところから地謡に任せられますから、やはり地謡の方が難しい。僕は親父に歯がたちませんでした。これは経験なのかなという気がいたします。
囃子方との信頼関係もなくてはダメですし、やはり、息の強さや間の正確さですとか、言葉の正確さもありますね。一体感といっても、うまくいく時と逆に合わせすぎて失敗することもあります。囃子方によっても違ってくることがたくさんありますし、最初から決めつけない方がいいなと思っています。例えば後見が物を取りに行くタイミングにしても、必ずといった決まり事でない限りは、毎回考えていくより仕方がないと思います。
大島 やはり舞台は生き物、ということですね。
いま謡のことを伺いましたが、私は光さん(鵜澤 光:銕仙会に所属する女性能楽師で、九世観世銕之丞の弟子にあたる)と「蝉丸【→演目事典】」でご一緒して先生にお稽古見ていただいた際に、謡いに対するご指導のあり方が細やかで、非常に深いなと感じました。特に息についての光さんへのご指導が非常に印象的でした。謡いに対して、ここが大事だということ、謡う時に大事にするべきことはございますか?
観世 「蝉丸」は盲目の高貴な青年であるので、盲目の役柄の息には一応テクニックとして習う部分があります。がさつに物を言わない、音をひとつも聞き漏らすまいとして話しているので、息は当然引くんだという解釈です。ただし、引けばいいというものではありません。例えば「景清【→演目事典】」だったとしても、荒々しい中にも、耳をそばだてているという感覚がないといけません。ですから「弱法師【→演目事典】」や「蝉丸」なんかは息を引く。
「蝉丸」は僕の好きな役どころでいろいろと思うところがあって、逆境に落ちていくことをずっと受け入れていく役柄なので、こういう謡い方がいいだろう、親父もこういうふうに謡っていただろうと指導したわけですね。
大島 役がおかれている状況や心境を読み込むということですね。
観世 謡いに関して言えば、まずはっきり詞が聞こえること。詞と言っても和歌が多いですから、実際には意味が分かると言うより詞のイメージですね。それが伝わるように息とともに送ってあげる。世阿弥の言葉にあるように、望憶の声の時に祝言のような声を出すことはあり得ないわけです。
声だとは言いますが、わたしは息だと思うんですね。例えば望憶の謡いだとしても、地謡がみんなメソメソした声を出したってうまくいきません。どんなに繊細なところを謡っていてもしっかり聞こえなければいけない。息がベースで声ができますので、しっかりできていた方がいい。地謡の場合は何人かで協同作業しなければならないので、地頭の時にあまり細い息で謡ってしまうと、周りの人も声が出せなくなってしまいます。「能は唄物語である、唄で進行している」と考えながら務めるべきだと思います。
寿夫の伯父も親父も、能の成功の7割方は謡の中にあるといわれるから、謡を疎かにしてはならんとよく言っていました。だからといって型は手を抜いてよい、ということではないので、結局両方ともやらなくてはいけません。(第1部 終/第2部へ続く)![]()

観世銕之丞氏が「好きな役どころ」という「蝉丸」。蝉丸(ツレ)は、延喜帝の第四皇子と高貴な出自の盲人。目が見えないゆえに音に敏感であるという意識を台詞にはらませながら、そこに気品も滲ませたいと語る。
観世流シテ方 九世 観世銕之丞(かんぜ てつのじょう)
1956年、八世観世銕之亟静雪(人間国宝)の長男として東京に生れる。名は暁夫。伯父観世寿夫、および父に師事する。4歳で初舞台、8歳で「岩船」の初シテを演じる。2002年、九世観世銕之丞を襲名。2008年「平成20年度(第65回)日本芸術院賞」、2011年「紫綬褒章」受章。銕之丞家当主および銕仙会棟梁としてこれからの能界を担う存在と期待され、力強さと繊細さを兼ね備えた謡と演技には定評がある。東京および京都、大阪でも活躍するほか、海外公演にも多く参加。重要無形文化財総合指定保持者。公益社団法人銕仙会代表理事。公益社団法人能楽協会理事長。京都造形芸術大学評議員。都立国際高校非常勤講師。漫画「花よりも花の如く」監修。著書に『能のちからー生と死を見つめる祈りの芸能』がある。
インタビュアー:喜多流能楽師 大島衣恵(おおしま きぬえ)
喜多流シテ方。能楽協会会員。1974年、東京生まれ。2歳の時に広島県福山市へ転居。同年、「鞍馬天狗」の稚児で初舞台。祖父久見(能大島家三代目)、父政允(四代目)に師事。1998年より、喜多流では初の女性能楽師として舞台活動を行う。以降、海外公演にも参加し、2005年「県民文化奨励賞」、2007年「広島県教育奨励賞」、2010年財団法人広島国際文化財団より「国際交流奨励賞」受賞。


