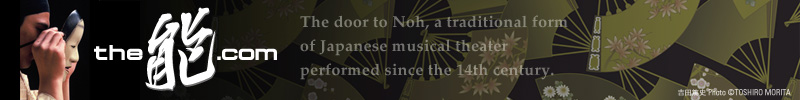
 ビジネスパーソンに捧ぐ世阿弥のことば
ビジネスパーソンに捧ぐ世阿弥のことば

世阿弥が残した『風姿花伝』を始めとする多くの著作は、演劇や芸術についての考えが述べられたものですが、世阿弥のことばの深さはそれだけではありません。今でいえば、「観世座」という劇団のオーナー兼プロデューサーでもあった世阿弥は、劇団の存続のためにはどうしたらいいかを考え抜きました。
それは役者の修行方法から始まり、いかにライバル劇団に勝ち、観客の興味をひくにはどうすべきかなど、後継者に託す具体的なアドバイスを記したものが、彼の伝書です。いわば、芸術のための芸術論というよりは、生存競争の厳しい芸能社会を勝ち抜くための戦術書ともいえるものです。
世阿弥は、観客との関係、人気との関係、組織との関係など、すべては「関係的」であり、変化してやまないものと考え、その中でどのように己の芸を全うするか、ということを中心に説いています。
「能」を「ビジネス」、「観客」を「マーケット」、「人気」を「評価」として読めば、彼のことばは、競争社会を生きるビジネスパーソンへの提言とも読めるのです。
世阿弥の珠玉のことばの中から、代表的なものをご紹介しましょう。
- 初心忘るべからず
初心忘るべからず
誰でも耳にしたことがあるこのことばは、世阿弥が編み出したものです。今では、「初めの志を忘れてはならない」と言う意味で使われていますが、世阿弥が意図とするところは、少し違いました。
世阿弥にとっての「初心」とは、新しい事態に直面した時の対処方法、すなわち、試練を乗り越えていく考え方を意味しています。つまり、「初心を忘れるな」とは、人生の試練の時に、どうやってその試練を乗り越えていったのか、という経験を忘れるなということなのです。
世阿弥は、風姿花伝を始めとして、度々「初心」について述べていますが、晩年60歳を過ぎた頃に書かれた『花鏡』の中で、まとまった考えを述べています。その中で、世阿弥は「第一に『ぜひ初心忘るべからず』、第二に『時々の初心忘るべからず』。第三に『老後の初心忘るべからず』」の、3つの「初心」について語っています。
「ぜひ初心忘るべからず」
若い時に失敗や苦労した結果身につけた芸は、常に忘れてはならない。それは、後々の成功の糧になる。若い頃の初心を忘れては、能を上達していく過程を自然に身に付けることが出来ず、先々上達することはとうてい無理というものだ。だから、生涯、初心を忘れてはならない。
「時々の初心忘るべからず」
歳とともに、その時々に積み重ねていくものを、「時々の初心」という。若い頃から、最盛期を経て、老年に至るまで、その時々にあった演じ方をすることが大切だ。その時々の演技をその場限りで忘れてしまっては、次に演ずる時に、身についたものは何も残らない。過去に演じた一つひとつの風体を、全部身につけておけば、年月を経れば、全てに味がでるものだ。
「老後の初心忘るべからず」
老齢期には老齢期にあった芸風を身につけることが「老後の初心」である。老後になっても、初めて遭遇し、対応しなければならない試練がある。歳をとったからといって、「もういい」ということではなく、其の都度、初めて習うことを乗り越えなければならない。これを、「老後の初心」という。
このように、「初心忘るべからず」とは、それまで経験したことがないことに対して、自分の未熟さを受け入れながら、その新しい事態に挑戦していく心構え、その姿を言っているのです。その姿を忘れなければ、中年になっても、老年になっても、新しい試練に向かっていくことができる。失敗を身につけよ、ということなのです。
今の社会でも、さまざまな人生のステージ(段階)で、未体験のことへ踏み込んでいくことが求められます。世阿弥の言によれば、「老いる」こと自体もまた、未経験なことなのです。そして、そういう時こそが「初心」に立つ時です。それは、不安と恐れではなく、人生へのチャレンジなのです。
- 男時・女時
男時・女時
世阿弥の時代には、「立合」という形式で、能の競い合いが行われました。立合とは、何人かの役者が同じ日の同じ舞台で、能を上演し、その勝負を競うことです。この勝負に負ければ、評価は下がり、パトロンにも逃げられてしまいます。
立合いは、自身の芸の今後を賭けた大事な勝負の場でした。しかし、勝負の時には、勢いの波があります。世阿弥は、こっちに勢いがあると思える時を「
男時 」、相手に勢いがついてしまっていると思える時を「女時 」と呼んでいます。向田邦子の小説集の題名として有名なこのことばは、世阿弥の造語です。
世阿弥は、「ライバルの勢いが強くて押されているな、と思う時には、小さな勝負ではあまり力をいれず、そんなところでは負けても気にすることなく、大きな勝負に備えよ。」と言っています。女時の時に、いたずらに勝ちにいっても決して勝つことはできない。そんな時は、むしろ、「男時」がくるのを待ち、そこで勝ちにいけ、というのです。
世阿弥は、この「男時・女時」の時流は、避けることのできない宿命と捉えていました。「時の間にも、男時・女時とてあるべし。」、「いかにすれども、能によき時あれば、必ず、また、悪きことあり。これ力なき因果なり。」
そして、「信あらば徳あるべし」──信じていれば、必ずいいことがある。と説いています。
- 時節感当
時節感当 これも、世阿弥の造語です。
ここでいう「時節」とは、能役者が、楽屋から舞台に向かい、幕があがり橋掛かりに出る瞬間を言います。幕がぱっと上がり、役者が見え、観客が役者の声を待ち受けている、その心の高まりをうまく見計らって、絶妙のタイミングで声を出すことを「時節感当」と言ったのです。
これは、タイミングをつかむことの重要性を語ったものです。どんなに正しいことを言っても、タイミングをはずせば人には受け入れられません。商談などの交渉事や、案件を上司に図る時など、「タイミングを逸して失敗した」といった経験は、誰にでもあるものです。タイミングが人の心の動きのことだとすれば、逸したのは、人の心をつかんでいなかったから、ということになるでしょう。
「これ、万人の見心を、シテ一人の眼精へ引き入るる際なり。当日一の大事の際なり。」(万人の目を主役に引きつけることが、何よりも大事だ。その「時節」に当たることが必要なのだ。)
正しいだけではだめで、その正しさを人々に受け入れてもらうタイミングをつかむことが必要なのです。
- 衆人愛敬
衆人愛敬
「衆人愛敬」とは、大衆に愛されることが一座の中心である、という意味です。
「いかなる上手なりとも、衆人愛敬欠けたるところあらんを、寿福増長のシテとは申しがたし。」(どんなに上手な能役者であっても、大衆に愛されることのない者は、決して一座を盛り立てていくことはできない)
当時、能は、「貴所」といって、貴族や武家の前で行うものでしたが、彼らに受け入れられているだけではいけない、と世阿弥は考えました。
「貴所、山寺、田舎、遠国、諸社の祭礼にいたるまで、おしなべて譏りを得ざらんを、寿福達人のシテとは申すべきや。」(貴族の前であろうと、山寺であろうと、田舎でも遠国でも、あるいは、神社のお祭りの時であろうと、どこでも喝采をうけるような演者でなければ、一座の中心として盛り上げる能の達人とはいえない)
どんなところでも、演じるたびに人々に拍手喝采をうける、そのような理想の姿は、父の観阿弥のものでした。何が求められているのか、その場その場の雰囲気を読み取り、自分をそれに合わせて能を舞う。観阿弥は、その術に長けていたようです。このような直感的能力がなければ、人気を保つことはできない、と世阿弥は言っているのです。
世阿弥が「衆人愛敬」といったもうひとつの理由は、自分の人気が失せた時の対策でした。
「万一少しすたるる時分ありとも、田舎・遠国の褒美の花失わせずば、ふつと道の絶ゆることはあるべからず」(どんなに都でもてはやされていても、自分ではどうしようもないめぐり合わせで「女時」となり、忍耐を強いられることもある。そんな時には、田舎や遠国での人気が支えとなり、自分の芸が絶たれてしまうことはない)
自分を支持してくれる大衆さえいれば、都の評判如何に関わらず、なんとかやっていける。自分の場が失われさえしなければ、挽回のチャンス(=男時)はあるのです。
- 離見の見
離見の見 自分の姿を左右前後から、よくよく見なければならない。これが「離見の見」です。「
見所同見 」とも言われます。見所は、観客席のことなので、客席で見ている観客の目で自分をみなさい、ということです。実際には、自分の姿を自分で見ることはできません。客観的に自分の行動を批判してくれる人を持つなど、ひとりよがりになることを避けるよう、心掛けなければなりません。
ではどうやって、自分を第三者的に見ればいいのか。世阿弥は、「
目前心後 」ということばを用いています。「眼は前を見ていても、心は後ろにおいておけ」ということ、すなわち、自分を客観的に、外から見る努力が必要だといっているのです。これは、単に演劇の世界に限ったことではありません。「後ろ姿を覚えねば、姿の俗なるところをわきまえず」(後姿を見ていないと、その見えない後姿に卑しさがでていることに気付かない)
それではいけない、と世阿弥は言っています。
歳を重ねれば重ねるほど、地位が上に行けば行くほど、前を見ることが要求され、自分の後姿を見ることを忘れてしまいがちですが、自分が卑しくならないためには、自分を突き放して見ることが必要なのです。
全体の中で自分を客観的に見ることは、いつの世でも難しく、しかし必要とされることなのです。
- 家、家にあらず。継ぐをもて家とす
家、家にあらず。継ぐをもて家とす
家というものは、ただ続いているだけでは、家を継いだとはいえない。その家の芸をきちんと継承してこそ、家が続くといえるのだ、という意味のことばです。
世阿弥は、「たとえ自分の子であっても、その子に才能がなければ、芸の秘伝を教えてはならない。」といった上で、このことばを続けています。激しい競争社会の中で、「家の芸」を存続させるには、このように厳しい姿勢が必要だったのです。
さまざまな分野で「二世」が闊歩する今日、この世阿弥の言は、もう一度噛み締める必要がありそうです。
- 稽古は強かれ、情識はなかれ
稽古は強かれ、情識はなかれ
「情識」(じょうしき)とは、傲慢とか慢心といった意味です。
「稽古も舞台も、厳しい態度でつとめ、決して傲慢になってはいけない。」という意味のことばです。世阿弥は、後生に残した著作の中で、繰り返しこのことばを使っています。
「芸能の魅力は、肉体的な若さにあり、一時のもの」という、それまでの社会通念を覆したのが、世阿弥の思想でした。それは、「芸能とは人生をかけて完成するものだ」という考えなのです。
「老骨に残りし花」は、観阿弥の能を見てのことばです。老いて頂上を極めても、それは決して到達点ではなく、常に謙虚な気持ちで、さらに上を目指して稽古することが必要だと、世阿弥は何度も繰り返し語っているのです。
慢心は、人を朽ちさせます。それはどんな時代の、どこの国にも当てはまることなのです。
- 時に用ゆるをもて花と知るべし
時に用ゆるをもて花と知るべし
物事の良し悪しは、その時に有用なものを良しとし、無益なものを悪しとする、という意味です。世阿弥は、この世を相対関係で考えていました。ここでは、美しさ、魅力、面白さなどさまざまなプラス概念を総合した意味で、「花」ということばを使っています。
- 年々去来の花を忘るべからず
年々去来の花を忘るべからず
「年々に去り・来る花の原理」とは、幼年時代の初々しさ、一人前を志した頃の技術、熟練した時代の満足感など一段ずつ上ってきた道で自然と身についた技法を全て持つことで、これを忘れてはならない、という意味です。
ある時は、美少年、ある時は壮年の芸というように、多彩な表現を示しながら己の劇を演ずるべきだ、と世阿弥は説いています。入門時から現在の老成期まで芸人は、その一生を自分の中に貯え、芸として表現しなくてはならない。日々の精進が大切なのです。
- 秘すれば花
秘すれば花
誰も知らない自分の芸の秘密、いわゆる秘伝を持つことを世阿弥は求めました。これをいたずらに使うことは控え、いざという時の技とすれば、相手を圧倒することができるというのです。
現代でも、自分の可能性を広げるための準備として秘する花を持てば、いざという時に世界が広がる可能性があるのです。
- 住する所なきを、まず花と知るべし
住する所なきを、まず花と知るべし
「住するところなき」とは、「そこに留まり続けることなく」という意味です。停滞することなく、変化することこそが芸術の中心である、と世阿弥は言っているのです。
- よき劫の住して、悪き劫になる所を用心すべし
よき劫の住して、悪き劫になる所を用心すべし
劫とは「功績」の意で、「良いとされてきたことに安住すると、それがむしろ悪い結果になってしまうことに用心せよ」という意味です。このことに、「よくよく用心すべし」と世阿弥は説いています。
世阿弥は、世間の変化の中で、その変化と関わりあっていくのが人間であり、芸術であると考えました。その変化の中で、変化することを恐れず、「住しない」精神を世阿弥は求めたのです。


