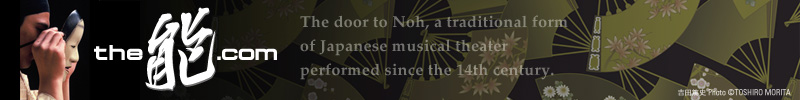
![「能楽図帖」 能[富士太鼓]](img/knd_fjdiko.jpg)
![]()
萩原院(花園天皇)に仕える官人が登場し、ある事件について語り出します。それは宮廷で催された七日間の管弦の催しをめぐっての出来事でした。宮廷では、太鼓の役には天王寺の楽人で浅間という者を召し出しましたが、別に、摂津の住吉から富士という名の太鼓の上手な楽人が、太鼓の役を望み、都までやって来ました。富士を取り立てようという人はいなかったのですが、浅間は富士の振る舞いを憎み、富士を殺害してしまったのです。官人は気の毒に思い、縁者が訪ねて来たら、形見の品を渡そうと思っていました。
ちょうどその頃、富士の妻と娘が都に上ってきました。妻は月夜に雨の降る夢を見て、不安を覚え駆けつけたのです。富士の行方を尋ね、官人のいるところを探し当て、面会することになりました。妻子と対面した官人は、富士が浅間に殺害されたことを伝えました。妻は気がかりな夢が本当だったと嘆き、残された娘を見て、止めどもなく涙を流します。
官人は富士の妻に、形見の品である舞装束を渡します。妻はその装束を見ながら、夫が勅を受けたわけでもないのに、高望みして出かけてしまったことが、このような結末になったと思いをめぐらし、無理にでも引き止めればよかったと深く後悔しました。その後、夫の形見の装束を身にまとった妻は狂乱し、太鼓こそが夫の敵だと言い出します。娘も父の敵と同調し、太鼓を叩きます。やがて富士の霊が妻に乗り移ったと見えて、娘に代わり、妻が太鼓を恨めしく叩き、さらには楽を舞いました。
恨みを晴らした妻は、御代を寿いで、千秋楽、太平楽を打った後、舞装束を脱ぎ捨て、太鼓こそ亡き夫の形見だと見つめ、帰途につきました。
![]()
夫婦、親子の別れが物語の底流にあり、そこに楽人同士の争いから生まれた殺人という悲劇的な要素も加わって、独特の趣を作り出しています。
殺人の当事者である富士(殺された者)、浅間(殺した者)のいずれも登場人物としては現れず、生々しい事件そのものが描かれることもなく、物語ははじめ、後日談として淡々と描き出されていきます。主人公は富士の妻。彼女は実際の仇である楽人・浅間に対して怒りや恨みをぶつけようとはしません。夫の行動を止められなかったことを後悔するばかりです。しかし理不尽な死別に対する行き場のない恨みはつのり、それが太鼓に向けられます。娘に太鼓を叩かせることで恨みを晴らそうとするのですが、恨みは晴れず、さらには富士の幽霊が憑依したとみえて、妻はなおも太鼓を打ちます。実際に憑依したかどうかはともかく、そのようにほのめかすことで、恨みの深さが強調されています。
この強烈な恨みを晴らす場面は、独特のテンポ、リズムで展開される謡、妻が夫の形見を着けて舞う緩急鋭い舞によって、異様な戦慄を持って描かれ、観る者の心をざわざわと波立たせます。ついには、彼らの恨みも晴れますが、太鼓を見つめる妻の姿は、言い難い余韻となって残ります。
激しい心の動揺から、静かな悲しみとも諦めともつかぬ余情へ。能の描き出す心象の陰影を、深々と感じていただけるでしょう。
類曲に富士の妻を亡霊として扱った夢幻能の「梅枝」があります。
▼ 演目STORY PAPER:富士太鼓
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
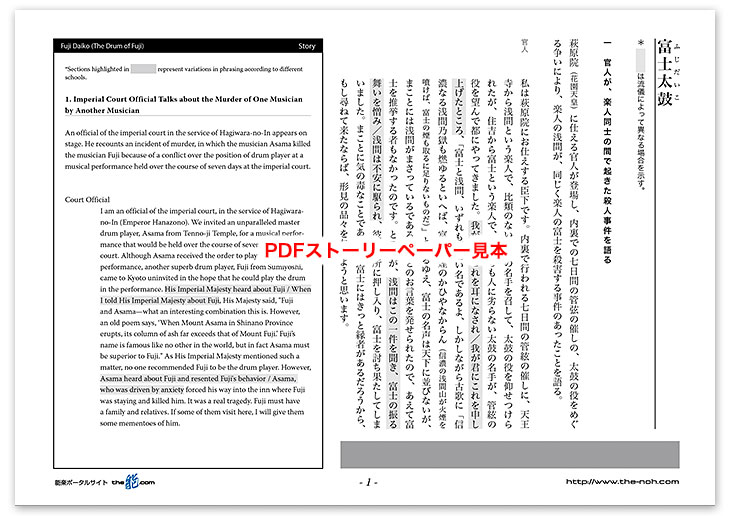
『能楽手帖』権藤芳一著 駸々堂
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社
各流謡本
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。



 [ 富士太鼓:ストーリーPDF:475KB
[ 富士太鼓:ストーリーPDF:475KB