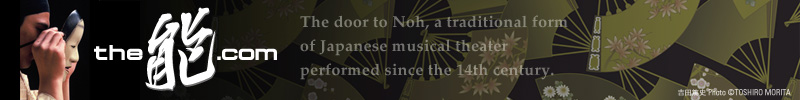
 Noh and International Cultural Exchange
Noh and International Cultural Exchange
4明治外交に花を添える

芝公園にあった料亭紅葉館に併設された能楽堂で「芝能楽堂」とも呼ばれた。1881年(明治14年)4月16日、宝生九郎による「高砂」か。
エジンバラ公アルフレッド王子、ハワイ王国カラカウア王、そして……
明治維新は、能に苦境をもたらした反面、新しい風を吹き込んだとも言えます。そのひとつが、外国人に日本文化の精華を伝える、外交的な役割でした。
幕藩体制の瓦解で能楽師が俸禄を失い、苦しい生活を強いられる一方で、能は外交舞台で活躍するようになります。外国賓客の来訪に際し、能が重要なもてなしとされ、演じられました。その役割を後押ししたのは、明治政府で外務卿、右大臣などを務めた岩倉具視。彼は1871年(明治4年)に岩倉使節団を組織して、73年(明治6年)まで欧米を視察しました。その折、西洋独特の楽劇であるオペラが、外国要人の饗応に催されることを知ります。日本では能がこれにあたると考えた彼は、能の再興と外交への活用を強く働きかけました。
ただ、能を外交のもてなしとすること自体は、欧米視察後の岩倉卿の肝煎りで始まったわけではありません。岩倉使節団が出発する2年前の1869年(明治2年)には早くも、外国賓客のために能狂言の催しが開かれました。その年の7月、明治政府は英国ヴィクトリア女王の次男、エジンバラ公アルフレッド王子を迎えます。その饗応に、相撲観戦や浅草訪問とともに、観能の催しが組まれました。赤坂の紀州藩別邸で演じられた能は、「弓八幡」(喜多勝吉)、「経正」(観世銕之丞)、「羽衣」(宝生九郎)、「小鍛冶」(金剛唯一)の四番。狂言も「墨塗」「太刀奪」の二番が出ました。また1872年(明治5年)10月のロシア帝国アレクセイ王子の訪日に際しては、「春日龍神」(宝生九郎)、「石橋」(観世銕之丞)、「舟弁慶」(中村平蔵)の三番が開催されました。翌1873年(明治6年)9月には、イタリア国王の甥、ジェノヴァ公を迎えて、「大蛇」「夜討曽我」「船弁慶」の能と、狂言「鼻角力」「素袍落」が演じられた、と外交文書に記録されています。
これら早い時期の外交舞台での饗応能は、能が後に勢いを盛り返す継ぎ穂になったと考えられます。その後1879年(明治12年)には、6月、ドイツ皇帝の孫を前田家で接待し、「橋弁慶」(梅若実)、「望月」(宝生九郎)、「吉野静」(蓑喜松)が組まれたのに続き、7月、アメリカのグラント将軍を迎えた岩倉邸での能狂言の宴もありました。1881年(明治14年)3月には、ハワイ王国のカラカウア王の前で、梅若実らによる能「紅葉狩」、「猩々」の二番と仕舞数番が演じられました。仕舞には荒い物も出されたようで、これこそ武士の舞いだ、面白い、とカラカウア王の拍手を得たと報道されています。同年11月には、京都に英国ヴィクトリア女王の孫であるアルバート王子、ジョージ王子(後の英国王ジョージ5世)を迎え、狂言二番「墨塗」、「腰祈」が演じられています。この年は芝能楽堂が開かれて能楽社が発足し、能楽復興が本格化した年でもありました。また1882年(明治15年)12月には、李氏朝鮮の修信使、朴泳孝氏らの帰国に際し、能狂言を催したと記録されています。
ニコライ皇太子の平癒祈願による演能も
1891年(明治24年)5月、ロシア帝国のニコライ皇太子(後のロシア最後の皇帝、ニコライ2世)の来日にも、能の催しが用意されていました。しかし、大津事件で皇太子が負傷したため、演能は取りやめになります。負傷したロシア皇太子の怪我が癒えるようにと、日本各地で祈願の催しがなされましたが、大津に近い彦根では、神社で平癒祈願の能も舞われたということです。日本人はそういう心情を持っていました。
1899年(明治32年)7月はドイツ帝国のハインリヒ親王を「橋弁慶」「石橋」等の演能でもてなし、1902年(明治35年)9月には、清国王族の貝子載振殿下を迎えた能狂言の催しがありました。以上、主に海外王侯のもてなしで演じられた能の記録を辿ってきましたが、これ以外にも、明治時代には、外交官、軍人、学者、芸術家その他、海外の賓客のために数多くの能が催されました。
長い鎖国の後に、海外との交流を再開して間もなかった明治時代。日本の外交活動には、多大な期待と不安とが同居していたことでしょう。これらの記録を目の当たりにすると、緊張感の漂う外交の場に、能がいわば「一掬の花」を差し、重要な文化交流、精神交流の役割を果たしてきたことが窺えます。外国の要人たちは、能のなかに日本の何を見たのか。興味深いところです。
【参考文献】
- 『明治能楽史序説』古川久 著(わんや書店 刊)
- 『明治の能楽(1)〜(4)』倉田喜弘 著(日本芸術文化振興会 刊)


