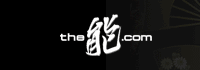 |
 |
 |
| > Top > ESSAY 安田登の「能を旅する」第9回 |
|
|
亡霊や精霊である“シテ”と 出会うところから始まります──。
連載「ワキから見る能の世界」では、
舞台でワキ方として活躍されている安田登氏に、
旅人・“ワキ”の目線から見た、能の世界を語っていただきます。
赤トンボと白蝶が意味するもの
 |
© greenrain2222 - Fotolia.com |
この連載のために、能の舞台となった名所旧跡(謡跡)を歩いていると、不思議なことがよく起こる。
前回、前々回と『平家物語』の一ノ谷の古戦場を歩いたときにも起こった。
* * *
ひとつは前にも書いたが、敦盛のことを思いながら、彼が亡くなった須磨の浦に立ったときだ。
海を眺めていると水上バイクが目の前に現れて海上を疾駆した。そして、それがちょうど敦盛が海に入り、熊谷直実に呼び戻されたあたりで止まったのだ。
そのおかげで「馬を海で泳がす平家」と、「馬で山を疾駆する源氏」の対比に気がつくことができた。
偶然のようではあるが、しかし不思議なことではある。
その翌日にも起こった。義経が鵯越の逆落としをしたといわれる、後ろの山に登ったときだ(前回の記事)。
山をぐるっと周り、義経鵯越の逆落としの最後のアプローチにかかったあたりに、ちょうど見晴らしのいい場所があった。そこらからは一ノ谷がすぐ下に見える。
石に座り、義経のことを思いながらiPhoneを取り出して、次のようなツイートをしていた。
「今でこそ蛇行する山道があるが、これがなかった当時は、ほぼ直角の山を七十騎で下りたのだろうか。しかもおそらくは足音を忍ばせて」
すると、どこからともなく赤トンボが飛んできて、私の右肩に止まった。
気にはなったが、ちょうどツイートしている途中だったので、気に留めずにiPhoneに向かっていると、赤トンボは肩から飛び立ち、今度はiPhoneの右上に止まった。
それでも気にせずにツイートを続けていた。赤トンボなんて珍しくはないような山中だ。が、シャカシャカと文字を打っているのに赤トンボは逃げようとしない。
さすがに不思議に思って、文字を打つ手をとめて赤トンボを眺めたとき、「あ、赤は平家の色だ!」ということに気づいた。平家は赤旗なのである。そこで、「この赤トンボの写真を撮っておこう」と思った途端に、赤トンボは突然いなくなった。
「残念だった」と思っていると、そこに今度は白い蝶が現れてゆったりと舞うのだ。
白といえば、むろん源氏である。
里人に身を変えて現れる能のシテは、中入りのときに旅の僧であるワキに向かって、「私の亡き跡を弔ってください(我が跡、弔ひてたびたまへ)」という。いま出現した赤トンボと白蝶も、旅人である私に向かい、その跡を弔うことを求めているのかも知れないと思い、能のワキ僧よろしく『観音経』を読経した。
 |
© Martina Berg - Fotolia.com |
偶然が意味を持ち始めるとき
人によっては、これはできすぎたフィクションかウソだと思うだろう。が、実際に謡跡を訪ねた人の中には、このような経験をした人は少なくないに違いない。
ただ、それに気づかないだけなのだ。
たとえば今、平家の象徴たる赤トンボが「右肩」に止まり、そしてiPhoneの「右上」に止まったという文を読み、「あ、平家の烏帽子は右折だ」と気づいた人もいるだろう。が、気づかない人もいる(ちなみにこれもフィクションではなく実際にそうだった)。
鵯越の山を歩いているときにも、たくさんの人と行き違った。言葉を交わしてみると、仕事をリタイアした人で健康のためにウォーキングをしている人が多かった。時間はたっぷりあるはずなのに、その方たちの歩きは速い。
義経の話を書いた立札を読むことはする。
が、「へぇ」なんて言いながら、敦盛や義経に思いを馳せるためにゆっくりと立ち止まることもなく、すたすた、すたすたと歩いて行く。赤トンボや白蝶にも気づかない。
赤トンボや白蝶なんて、あの山にはたくさんいる。その出現はむろん偶然だし、驚くべきことではない。
が、それをどのように感じるかで、偶然は意味を持ち始める。
ただのトンボや蝶だと思うこともできるし、平家と源氏とみることもできる。むろん後者の方が人生は楽しい、と私は思う。
謡を知り、能をよく観ている人ならば、私と同じことに気づく素地はすでにある。あとはゆったりと古事に思いを馳せるだけでいいのだ。
それに気づくか、気づかないか
能には鎮魂の物語が多い。
能、特に夢幻能に出現する亡者たちは、鎮められるべき魂をもった死者たちである。この世に思い(念)を残したまま死んだ「残念な亡者たち」である。そんな彼らがこの世に再び現れ、旅人の求めによって昔を語り、思いを吐露し、舞を舞い、そして残恨の思いを晴らして、再び彼岸に戻る、それが能だ。
能はエンターテイメントであると同時に、鎮魂の芸能なのだ。
だから謡跡を巡る旅も、物見遊山というよりは、やはり鎮魂の旅として歩く。
一ノ谷の合戦の跡を巡ったあと、その次の大合戦の場だった四国の屋島に向かった。
まさか一ノ谷で源氏に大敗を喫するとは思わなかった平家の一門は、再起をはかって四国の屋島に陣を構えたのだ。
ここでの戦いのさまは能『屋島』などに描かれるが、その話は次回にすることにして、今回は不思議話の続きとして、屋島で出会った老人の話をしよう。
さて、まずは能『屋島』にまつわる、さまざまな旧跡を尋ねようと、主に古戦場を中心にいろいろ歩き回った。
そのあと、佐藤継信の墓に参ろうと思っていた。
佐藤継信は『おくのほそ道』の中でも触れられる重要な人物であり、芭蕉好きの私としてはかなりの思い入れがある。
継信は、もとは奥州藤原氏に仕えていた、陸奥、すなわち東北の武将だ。
鞍馬山から下りた義経は、弁慶らとともに、一時、奥州藤原氏に身を寄せていた。それが、兄、頼朝の招集によって鎌倉に向かったとき、佐藤継信も主君の命により義経に従うことになった。
そして、佐藤継信はこの屋島で壮絶な戦死を遂げる。源義経に向けて射られた矢を、自分のからだに受けて死んだのである。
継信の墓はふたつある。ひとつは簡単に見つかったが、ふたつめがなかなか見つからない。あちこち歩き回ったが見つからない。そこで土地の人に尋ねることにした。
子どもたちに聞いたが知らないという。そこにひとりのお年寄りが通りかかったので、「佐藤継信の墓はどこですか」と尋ねた。すると「そら、そこに」と、自分がいたすぐ上の丘の上を指差した。
 |
© Cozyta - Fotolia.com |
礼をいって、坂道を登り始めたが、背後に人の気配がする。ふと振り返ると、さっきの老人がついてきている。
そして「わたしが、後をついてきたのはな、ほかの墓も教えようと思ってなのだ」という。
いま、思い出しながら書いていると、なんとも不思議な老人ではあるが、そのときは全く不思議には思わず、教えられるままについていった。
そこにはまず佐藤継信の墓があった。
が、その少し上に小さな墓石具群とお堂があった。
「これは四国遍路で行き倒れになった方のお墓だ」と教えてくれ、「せっかくなので、ここもお参りしたらいいだろう」というので、数珠を取り出して、お経を低く誦した。
するとまた継信の墓に戻り、「周りを見てみろ」といわれて眺めれば、継信の墓の周囲には、いくつもの墓が並んでいる。その墓には、みな星がついている。これは日清、日露、太平洋戦争で亡くなった方たちのお墓だという。
さらにその墓所を取り囲むように、小さな石碑群が立っている。見れば牛の絵が彫られている。
「これは借耕(かりこう)牛の墓だ」という。
他の土地から借りて来た牛だが、もとの土地に返せぬままに死んでしまった牛の墓だという。
「佐藤継信も、四国遍路の人たちも、大戦で亡くなった英霊たちも、そして借耕牛もみな故郷に帰れず亡くなった。その墓がここに並んでいるのだ」
老人はそう言って、もと来た道を帰って行った。
故郷で死ぬことができなかった魂を祀る高台から見渡せば海が開けている。「異郷で亡くなった人の魂は海を眺めているんだな」と思いながら、数珠を取り出して念仏をした。
まるで能のような話だ。
自分で書いておきながら、あまりにでき過ぎた話ではある。
しかし、能の旧跡を訪ねる旅をする人の中には、似たような体験をされた方が大勢いらっしゃるのではないだろうか。
何度も書くが、それに気づくか、気づかないかだけである。
(2013年9月)
安田登 プロフィール
1956年生まれ。能楽師、ワキ方、下掛宝生流。公認ロルファー(米国のボディワーク、ロルフィングの専門家)。著作に『異界を旅する能』
『身体能力を高める「和の所作」』
『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。』
『対談 前田英樹×安田登 からだで作る〈芸〉の思想』
など多数ある。
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.