 |
 |
 |
| > Top > ESSAY 安田登の「能を旅する」第8回 |
|
|
亡霊や精霊である“シテ”と 出会うところから始まります――。
連載「ワキから見る能の世界」では、
舞台でワキ方として活躍されている安田登氏に、
旅人・“ワキ”の目線から見た、能の世界を語っていただきます。
五感すべてで死の世界をかいまみる合戦場面
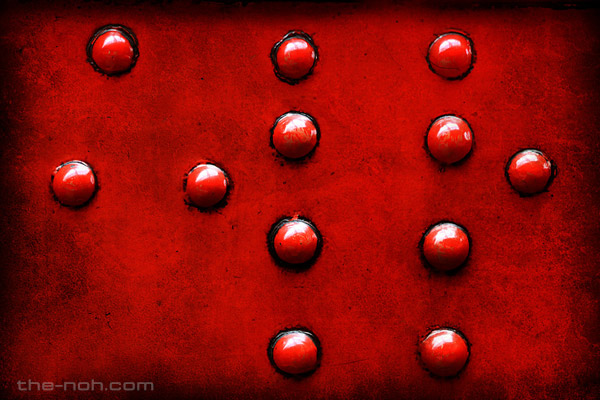 |
© INFINITY - Fotolia.com |
前回は、海上を疾駆する水上バイクに、須磨の浦を馬で泳ぐ平敦盛を幻視した。
能にも『平家物語』にも「前は海、後は山」とあるように、海を眺めたあとは、やはり後ろの山に登りたい。敦盛塚の最寄り駅である須磨浦公園駅から、海とは反対側にある山に登っていくと、鉢伏山、旗振山、そして鉄拐山、高倉山へと続きます。春や秋には、ちょうどいいハイキングコースです。
一ノ谷の合戦では、敦盛をはじめとする平家の武将のさまざまな死も印象的ですが、もうひとつ私たちの目を引くのが義経の鵯越(ひよどりごえ)の逆落としです。そして、この山が、義経の鵯越の逆落としの現場といわれている名所なのです。
能では、この鵯越の逆落としは、『景清』、『摂待』、そして『通盛』の中で触れられてはいますが、そのものを扱う作品はありません。それがなぜなのかは次回に扇の的の旧跡巡りとともにお話することにして、今回は『平家物語』から「義経の鵯越の逆落とし」のところを読んでみましょう。
一ノ谷の合戦は、最初は互角。熾烈な戦いが続きます。まずはその戦いの描写から。
ここまでのさまざまな戦いが描かれたあと、「源平乱れあい、入れかえ入れかえ、名乗り替え名乗り替え」と書かれます。戦場で鎧と鎧のぶつかる音、そして大声で名乗りをする声々、そういうさまざまな音が響き合いますが、これは『平家物語』お得意の音の描写。
音は、それだけではない。「馬の馳せちがう音は雷のごとし」という。
「雷のごとし」というのは大げさな表現ではないでしょう。耳を聾するばかりの蹄の音、そして馬と馬のぶつかる音、馬たちの嘶(いなな)く声。数頭の馬が疾駆する競馬場でも近寄れば馬の息だけでもすごいのに軍馬がぶつかり合う戦場。ぶるぶるっという息の音に高い嘶き声、体のぶつかる音、蹄の音、これらを数千、数万の馬が発すると思えば、それはまさに「雷のごとし」。それに人々のおまき叫ぶ声が交じるわけですから、想像を絶する音が響いていたでしょう。
これに続く『平家』の文には「射違うる矢は、雨の降るに異ならず」とあります。雨のように矢が降ってくる。これだけでも怖い。それに空気を引き裂く無数の矢の音もする。さらに怖い。さらに「矢さけびの声、山を響かし」とありますから、矢を射る人々の「おー」という声が山を響かせている。
人、馬、矢と、ものすごい音が鳴る。音に続いて戦いの描写。
「あるいは軽傷のままに戦う者もあり。あるいは負傷した者を肩に引っかけて退く者もあり。引っ組んで戦い、相手と差し違えて戦死する者もあり。あるいは敵を取って押さえ、その首を掻く者もあり、あるいは首を掻かれる者もあり」
まさに血で血を洗う戦場です。読んでいるうちに血の匂いがぷーんと漂ってきます。五感すべてが死の世界に投げ込まれたような合戦場。
戦いは互角とはいえ時の利はすでに源氏にある。しかし、平家の布陣は山を背とし、海を前にし、敵の侵入は狭い左右を許すのみという定石通り。攻めれば攻めるほど源氏側の死傷者は増えるばかり。源氏は攻めあぐねている。
鬼神のごとき義経の鵯越の逆落とし
この状況を打ち破るには平家の背後を突くしかありません。しかし、それには急峻な坂を駆け下りなければならない。義経は一万余騎を二手に分けて、自身は三千余騎で、一ノ谷の後ろの山に登り、眼下に布陣する平家の城郭を見下ろす。
突然現れた兵に驚いた鹿が三頭、山から下りていった。下にいる平家の陣地では、上の山から鹿が下りて来たので「上に敵がいるのでは」と不審がる。
いいところに気づきました。ここで手を打っておけば大事には至らなかったのですが、ここが平家に利あらざるところ。それをちゃんと確かめもせずに、三頭のうち二頭を射留めたりしているうちに、うやむやになってしまう。平家の運も尽きという感じです。
さて、山上にいる義経は「馬を落としてみよ」と言い、鞍を置いたままの馬を十頭ほど崖の下に落とす。無事に崖下まで下る馬もあれば、足を折って死ぬ馬もある。そんな中に崖の下にある越中前司の館の上で、ぶるぶるっと身震いして立った馬が三頭あった。
これを見て「乗り手が心得ていれば、この崖も下りることができる。我が下りざまを手本にせよ」と、まず三十騎ばかり、真っ先駆けて落ち行けば、残りの大軍もこれに続く。
何しろ急峻な崖です。前の者の鎧や甲に、後ろに続く馬の鐙がぶつかるほどの勢いで、小石まじりの真砂の崖を、流れ落としにざっざっとばかり二町ほど一気に駆け下りて、壇のような踊り場に馬を控えた。
が、これがまずかった。一度止まったおかげで下が見えてしまった。見下ろせば、大磐石の苔蒸したるが釣瓶落としに、ずいっと垂直に十四丈(40メートル強)あまり続いている。ビルの高さでいえば10階。そこから垂直に下を見る。しかも馬に乗っているわけですから、これは怖いですね。
引くに引かれず、下りるに下りられず、呆然としていると、そこにつかつかと進み出てきたのが、三浦の佐原十郎義連。
「我が故郷、三浦では、このくらいのところは馬場のようなもの。何のことはない」と、真っ先駆けて下って行く。その勢いに大軍もこれに続く。が、慣れない者には恐ろしい。目を閉じて下りて行く者もあったという。
『平家物語』の作者は「おおかた人のしわざとは見えず、ただ鬼神のしわざととぞ見えたりける」と言っています。
鬼神のごとき義経軍、全軍が下りた所で、どっと鬨の声をあげる。三千余騎の声ではあるが、山彦も応えて十万余騎の声と聞こえた。
その声に平家の人々がひるんだところに、義経らは平家の屋形、仮屋に付け火をしてみな焼き払う。折節風は激しく、黒煙が押しかかるので、平家の兵たちはみな海の方に逃げます。
波打ち際には平家の「助け船」がたくさん控えていたが、さすがに船一艘に鎧・兜に身を固めた武将達が、あるいは四五百人、あるいは千人も乗れば、たまったものではない。三町ほど行ったところで、大船が三艘沈んでしまった。
それから後は船の方でも用心する。
「身分の高い人を乗せよ。雑人どもは乗すべからず」
そう命じて、舟に乗ろうとする雑人どもを太刀、長刀で切り払う。が、戻れば源氏が待っている。乗せじとすれども船に取り付くのは人情。そんな雑人の、あるいは肘を打ち切り、あるいは腕を打ち落とす。そんなわけで一の谷の波打ちは、肘や腕のない雑人の死骸で朱に染まったという。
この戦場はついに、味方が味方を殺害するという修羅の巷になってしまった。
そして、この急襲がきっかけとなり一ノ谷の合戦は源氏の大勝となったのです。
 |
© Edoma - Fotolia.com |
『曲垣平九郎・誉れの石段』の実験からわかること
ここで話の腰を折るようですが、どうもこの話、眉唾ではないかという説もちらほら。
さきほど「この山が、義経の鵯越の逆落としの現場といわれている名所」と書きましたが、現在の鵯越は、ここ一ノ谷の城郭までは8キロも離れています。そんな遠いところから逆落としなどというのは変だ、というのがまず第一の説。
それに対して、いやいや一ノ谷の位置自体が違うのであって、鵯越はここでいいという説もあります。
あるいは一ノ谷は、やはりここで、逆落としは現在の鵯越からではなく、一ノ谷のまさに後ろの山、すなわち旗振山、鉄拐山、鉢伏山のあたりからされたという説を唱える人もいます。
が、それならばそれで、実際に行ってみればわかるのですが、とてもとても馬が下りられるような崖ではない。そこでこの話自体がフィクションではないかという説もある。
私は学者ではないので、どの説が正しいのかの判断はしかねますが、しかし急峻な崖だって逆落としはできたのではないかと思うのです。
さて、急な坂を馬で上り下りしたといえば、講談・浪曲ファンならばご存知、寛永三馬術のひとつ『曲垣平九郎・誉れの石段』です。
寛永年間、将軍徳川家光公が秀忠公の三回忌で増上寺にご参拝した、その帰り、芝の愛宕山(港区)を通り過ぎた。そのとき山上に梅が見えた。
「誰か馬で取って来い」との将軍の命令に、各藩の馬術の名人三人が試みた。が、愛宕山の山上には家康公ご創建の愛宕神社があり、そこに続く86段の急な石段がある。馬術の名人たちはみな失敗。馬もろとも石段から落ちた。
あきらめて後日を期して帰ろうとするときに、いかにも駄馬に乗った痩せた侍がひとり、「我こそは」と名乗り出た。
将軍は「名だたる名手たちが失敗しているのに、まさかこの痩せ侍が」と思ったが、彼こそ四国丸亀藩に仕える馬術の名手、曲垣平九郎。平九郎は見事、馬を操ってタッタッタッと駆け上がり、山上、愛宕神社境内に咲く紅白の梅を手折り、そして再び馬にて駆け下りて、家光公に梅を献上した。平九郎は公から「日本一の馬術の名人」と称されたと伝えられています。
義経の逆落としは約40メートル、愛宕山は約30メートルと10メートルの違いはありますが、しかし愛宕山から下をのぞいてみると、とてもとても馬で下りられるとは思えない。「講談師、見てきたような嘘をいい」というように、この話も講談師や浪曲師の作り話ではないかと思われていたのですが、「なら、試してみよう」と昭和五十七(1982)年に日本テレビの企画で、果たして馬での上り下りが可能であるかの実験が行われたのです。
実は、この石段のある愛宕神社は、私の能の先生である鏑木岑男師が宮司をされている神社です。昭和五十七年は、ちょうど先生のお宅に通い始めた時期でしたので、この試みを間近で見ることができました。
先生からの要望で、万が一落ちても人馬ともに安全なようにと安全網などがつけられて実験開始。
結果は大成功。しかもかなりの短時間での上り下りでした。
 |
© Cozyta - Fotolia.com |
能ではあっさりとしか扱われない「鵯越の逆落とし」
これを見たときに「逆落としは本当にあった可能性が高い」と確信しました。史実はともかく可能ではある。
テレビではここに至る道のりも放送されました。馬も騎手も、したことのない試みです。数段の階段からの練習を何カ月も続けて、この成功をゲットしたのです。
そして、このこと、すなわち昭和の騎手や馬は、その稽古に何カ月もかかったということと、そして稽古さえすればそれが可能であるということこそが、『平家物語』における、このくだりの面白さなのです。
三浦の義連たちにとっては、一ノ谷の後ろの山がいくら急峻な崖であろうとも、ふだんの馬場のようなもの、なんともなかった。彼らは昭和の騎手や昭和の馬のように、訓練をする必要はなかった。むろん、馬自体も現代のそれとは違っていたが、それだけではない。崖だといわれても「これが崖?」くらいの気持ちだったのでしょう。
前回にも書きましたが、私は海辺の育ちです。かつてはうちの前の海は、よそから来た海水浴客が毎年ひとりずつ亡くなりました。波が渦を巻いていたり、岩があったりするからです。しかし、そこで育った私たちにとって平気も平気。そんなところで亡くなる人の方がよくわからない。
おそらく三浦一族もそうだったのでしょう。そして、これは三浦一族だけではなかった。後に扇の的で有名になる那須の与一も、やはりこの程度の崖はそんなに苦ではなかったはずだし、義経の親衛隊である奥州藤原氏だって、都に輸出するほどの馬の名産地のつわものども。そしてあの地形の中で馬を走らせていれば、このくらいの崖はたいしたことがなかったのではないか、そう思うのです。
すなわち源氏の兵士たちは、馬で山を走ることに長けていた人たちだったのではないでしょうか。
さて、ここで前回を思い出していただきたい。平家一門は、馬に海を泳がせる名手たちだった。それに対して源氏は山を走らせる名手たち。
馬という、当時、最大、最強の武器を媒介に、一方では馬を海で泳がすことにたけていた平家と、かたや山を駆けさせる源氏。前者の代表が平敦盛ならば、後者の代表は鵯越(ひよどりごえ)の逆落としで勇名を馳せた源義経です。
そして私がとても興味があるのは、この鵯越の逆落としという、能にすれば見どころ満載のこの場面を、能ではやけにあっさりとしか扱っていないということなのです。
『敦盛』の型の中には、両手で手綱を操り、馬を引き返す型があります。これを使えば、非常に面白い仕舞ができると思うのですが、それをしない。
どうも能作者は、この場面に冷淡であるようなのです。さて、それはなぜなのか。そこら辺のことも含めて、次回は四国、屋島の合戦場に足を伸ばしてみましょう。
(2013年4月)
安田登 プロフィール
1956年生まれ。能楽師、ワキ方、下掛宝生流。公認ロルファー(米国のボディワーク、ロルフィングの専門家)。著作に『異界を旅する能』
『身体能力を高める「和の所作」』
『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。』
『体と心がラクになる「和」のウォーキング』
など多数ある。
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.