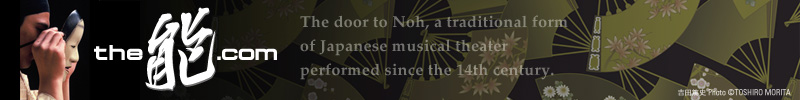

![]()
木曽の僧が都に上る途上、琵琶湖のほとりの粟津が原というところに差し掛かります。そこで神前に参拝に来た女と出会いますが、女が涙を流しているので不審に思い、理由を尋ねます。女は古歌を引き、神前で涙を流すのは不思議なことではないと述べ、僧が木曽の出だと知るや、粟津が原の祭神は、木曽義仲(源義仲:1154〜1184)であると教えて供養を勧めます。そして、自分が亡者であることを明かし、消えてしまいます。
僧はお参りにきた近在の里の人(所の者)から、義仲と巴の物語を聞き出し、先の女の亡者が巴だと確信を深めます。
夜になり、僧が経を読み、亡くなった人の供養をしていると、先ほどの女が武者姿で現れます。女は巴の霊であることを知らせ、主君の義仲と最期を共に出来なかった恨みが執心に残っていると訴えます。そして義仲との合戦の日々や、義仲の最期と自らの身の振り方を克明に描き、執心を弔うよう僧に願って去って行くのでした。
![]()
戦場を駆ける女武者、というと何とも勇ましい女丈夫のイメージが浮かびます。けれど能のなかで巴は、主君の木曽義仲を一途に慕い、愛し、その真っ直ぐな思いをひたすらに訴える一人の女として描かれます。確かに戦場での鬼神のような強さ、逞しさも見せますが、かえってそれは、巴の深い思いを際立たせます。
前半の静かな始まりと問答によるほのめかしから一転、後半は強吟、弱吟が交錯し、緩急、変化に富む素晴らしい謡が展開されます。そしてシテは決して派手に動かず、多少の立ち回りを除いては目立った舞いもなく、能らしく短く練られた所作を連ねます。そのすべてが、巴の哀しい運命と心情を切々と描き出して、彼女の色々の思いが、濃淡細かく観る者、聴く人の心に迫ります。
不思議なことに、この「巴」という曲は、もちろん心に響く度合いに違いはありますが、練達者のレベルの高い舞台、修業途上の演者の若々しい演技、あるいは素人が懸命に謡う素謡や連吟と、いつどれを見聞きしても泣けます。まして謡を習い、自分で謡えるならば、巴の哀切に身を切られないことはないでしょう。それほどの力のある曲ですから、名手の上手な能に出会う機会があったら、本当に幸せなことです。
▼ 演目STORY PAPER:巴
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
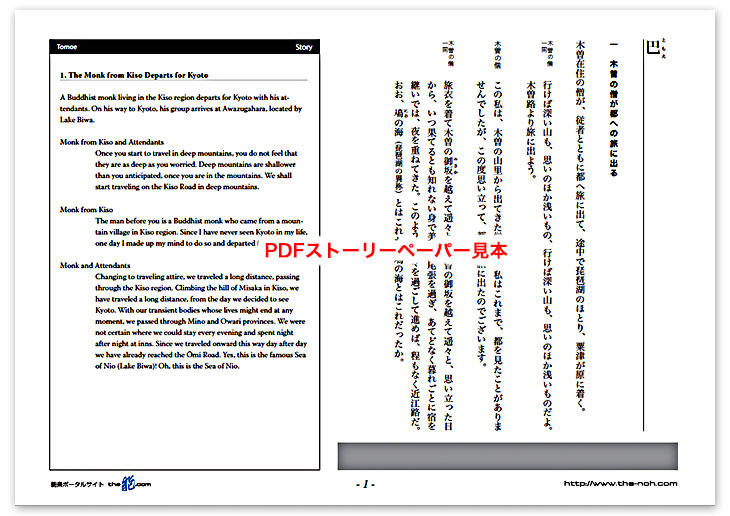
『能楽手帖』権藤芳一 著 駸々堂
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
『能への招待 II』藤城繼夫 文 亀田邦平 写真 わんや書店
『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。



 [ 巴:ストーリーPDF:453KB
[ 巴:ストーリーPDF:453KB