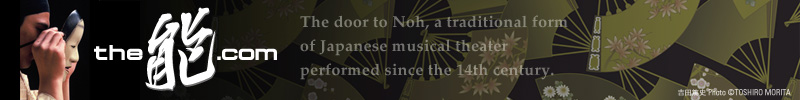

![]()
秋の名月の日。都に上った東国の僧が、六条河原院まで来たところ、ひとりの汐汲みの田子を背負った老人が現れます。六条河原で汐汲みとは、と訝る僧に、老人は、この河原院はかつて河原左大臣といわれた源融(みなもとのとおる)が、陸奥千賀の塩竃の景色をそのまま都に移して作って住んだところだと謂れを語るうちに、月が出てあたりを照らし、趣深い秋の夕景色がふたりの眼前に広がります。
庭の景色を眺めつつ、僧と老人がなおも言葉を交わします。融は、毎日難波から潮を汲ませて、院の庭で塩を焼かせて一生の楽しみとしたが、後を継ぐ人もなく、この河原院は荒れ果ててしまった……。そう嘆く老人を慰めようとしたのか、僧は都の山々の名所を教えてほしいと頼みます。あちこち挙げながら、一緒に仲秋の名月を愛でるうち老人は、つい長話をしたと言って水を汲む様子を見せた後、姿を消してしまいます。
近くに住む者から、河原院と融の大臣(おとど)の物語を聞いた僧は、先ほどの老人が大臣の亡霊だったと思い当たり、眠りにつきます。すると在りし日の姿で融の亡霊が現れ、月光に照らされながら華麗な遊楽に乗って舞うのでした。融は、時を忘れたかのようにこの月夜に興じていましたが、夜明けとともに、名残惜しい面影を残して、再び月の都へ戻っていきました。
![]()
源融(みなもとのとおる)は、嵯峨天皇の十二皇子で、「源氏物語」のモデルになったとも言われる人です。臣籍に入り、左大臣まで務めますが、そのころ台頭してきた藤原氏との政権争いに負け、六条河原に大邸宅を造営し、余生を風雅のうちに過ごしました。この能でも語られるように、陸奥の塩竃の風景を愛し、これを自宅の庭に模して、毎日難波津から潮水を運ばせ、塩を焼いたと言われています。その死後も、河原院への執着が断ちがたく、幽霊となって現れ、後の所有者である宇多上皇の御息所を悩ませた話が宇治拾遺物語に出てきます。
観阿弥、世阿弥の時代、融の大臣(おとど)は、河原院にとりつく怨霊、鬼のイメージがあったようですが、この能では、風雅を愛した人物像に焦点を当て、月の都に住まう貴人という幻想的な融の姿を創りだしています。
一曲を通して取り立てて変化のある物語はなく、シテは老人から貴人へと役を替えながら、名月の輝く秋の風景のなかで、懐旧の情を帯びつつも、ただひたすら美を紡ぎ出すことへ収斂していきます。それを囃子、謡が盛り上げ、舞曲で風雅を表す様は、能が音楽であり、舞踊であり、詩であり、そのいずれもが重なって創られる美そのものだと感じさせてくれます。
▼ 演目STORY PAPER:融
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
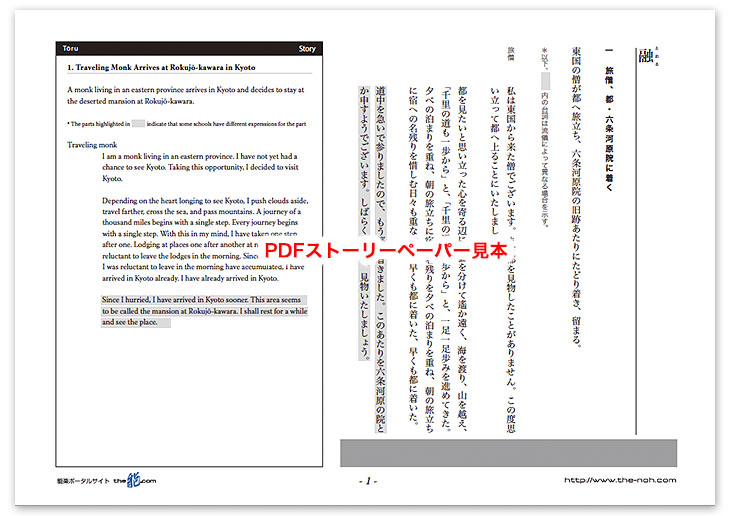
『日本古典文学大系 謡曲集 上』横道萬里雄・表章 校注 岩波書店
『新潮日本古典集成 謡曲集 中』伊藤正義校注 新潮社
『日本古典文学全集33 謡曲集(二)』小山弘志・佐藤喜久雄・佐藤健一郎 校注・訳 小学館
『能楽手帖』権藤芳一 著 駸々堂
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
『能への招待 I』藤城繼夫 文 亀田邦平 写真 わんや書店
『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。



 [ 融:ストーリーPDF:799KB
[ 融:ストーリーPDF:799KB