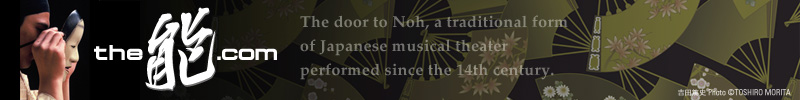

![]()
諸国を巡る僧が、三河国に着き、沢辺に咲く今を盛りの杜若を愛でていると、ひとりの女が現れ、ここは杜若の名所で八橋(やつはし)というところだ、と教えます。僧が八橋は、古歌に詠まれたと聞くが、と水を向けると、女は、在原業平が『かきつばた』の五文字を句の上に置き、「からころも(唐衣)き(着)つつ馴れにしつま(妻)しあればはるばる(遥々)きぬるたび(旅)をしぞ思ふ」と旅の心を詠んだ故事を語ります。やがて日も暮れ、女は侘び住まいながら一夜の宿を貸そう、と僧を自分の庵に案内します。
女はそこで装いを替え、美しく輝く唐衣を着て、透額(すきびたい)[額際に透かし模様の入ったもの]の冠を戴いた雅びな姿で現れます。唐衣は先ほどの和歌に詠まれた高子(たかこ)の后のもの、冠は歌を詠んだ業平のもの、と告げ、この自分は杜若の精であると明かします。
杜若の精は、業平が歌舞の菩薩の化身として現れ、衆生済度の光を振りまく存在であり、その和歌の言葉は非情の草木をも救いに導く力を持つと語ります。そして、伊勢物語に記された業平の恋や歌を引きながら、幻想的でつややかな舞を舞います。やがて杜若の精は、草木を含めてすべてを仏に導く法を授かり、悟りの境地を得たとして、夜明けと共に姿を消すのでした。
![]()
在原業平が「かきつばた」の五文字を和歌に詠み込んだ、という話を聞くと、自然の情景と結びつく、日本の言葉の美しさを思わせられます。大和言葉の持つ情感の豊かさ、詩性をよく表していると言えるでしょう。
「杜若」は、シテ[杜若の精]とワキ[旅僧]のみが登場し、夢幻能ではめずらしく一場で展開する簡潔な曲です。花の精の女性のシテが、上記の、『伊勢物語』に記された東下りエピソードを軸に、在原業平の華麗な恋の数々と仏の功徳を結び、深い夢に入り込むように、幻想的に謡い舞うところが、大きな見どころです。
大和言葉の醸す詩的な情感に、杜若の表す初夏のさわやかな季節感、雅な貴族文化の香気を絡めた一時のまぼろしを、洗練された詞章や音楽、きらびやかな装束、しっとりした舞でお楽しみください。
▼ 演目STORY PAPER:杜若
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
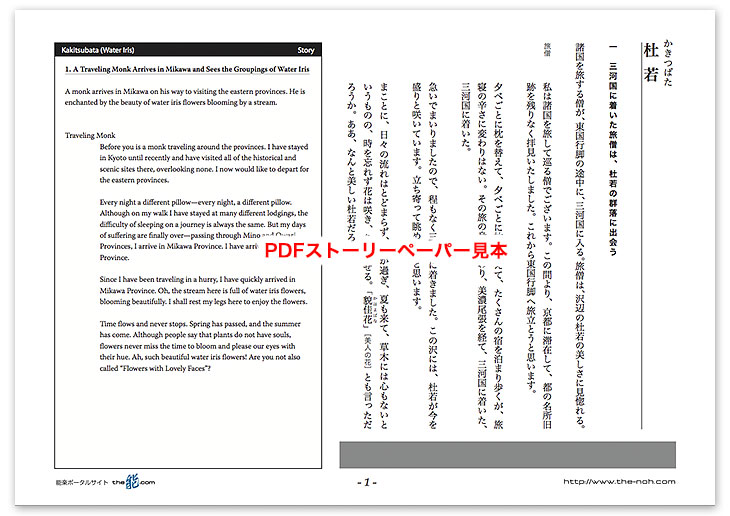
『新潮日本古典集成 謡曲集 上』伊藤正義・校注 新潮社
『解註 謡曲全集 巻2』野上豊一郎・編 中央公論社
『能への招待 II』藤城繼夫・文 亀田邦平・写真 わんや書店
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。



 [ 杜若:ストーリーPDF:570KB
[ 杜若:ストーリーPDF:570KB