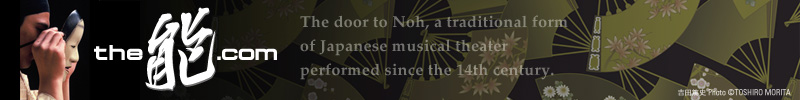

![]()
平家一門が都落ちした後、都でひっそり暮らしていた平清経の妻のもとへ、九州から、家臣の淡津三郎(あわづのさぶろう)が訪ねて来ます。三郎は、清経が、豊前国柳が浦〔北九州市門司区の海岸、山口県彦島の対岸〕の沖合で入水したという悲報をもってやって来たのです。形見の品に、清経の遺髪を手渡された妻は、再会の約束を果たさなかった夫を恨み、悲嘆にくれます。そして、悲しみが増すからと、遺髪を宇佐八幡宮〔現大分県北部の宇佐市〕に返納してしまいます。
しかし、夫への想いは募り、せめて夢で会えたらと願う妻の夢枕に、清経の霊が鎧姿で現れました。もはや今生では逢うことができないふたり。再会を喜ぶものの、妻は再会の約束を果たさなかった夫を責め、夫は遺髪を返納してしまった妻の薄情を恨み、互いを恨んでは涙します。やがて、清経の霊は、死に至るまでの様子を語りながら見せ、はかなく、苦しみの続く現世よりは極楽往生を願おうと入水したことを示し、さらに死後の修羅道の惨状を現します。そして最後に、念仏によって救われるのでした。
![]()
世阿弥が出家する以前の自信作のひとつで、現代でも修羅能の代表的な一曲です。亡霊のシテが妻の夢に現れるという設定ですが、前シテが後シテの化身という設定の複式夢幻能とは異質の、現在能的な作風です。
世阿弥は、その著『風姿花伝』や『三道』で、修羅能の作り方として、源平の名将を主人公に、物語を元のままに作ること、終曲部に合戦の場面を置くこと、などを説いています。しかしながら、平家の公達とはいえ、入水による死を選んだ清経は、上記の定型的な修羅能の主人公のイメージからは離れています。都落ちした平家一門への喪失感と絶望感に苛まれた清経は、信仰による究極の救いを求めます。自ら死を選んだ清経の心情は、回想のかたちで語られます。シテの、この心象風景と、実際の情景とを織り交ぜた、クセからキリにかけての舞の部分が一番の見どころといえるでしょう。張りつめた緊張感のなか、地謡、囃子とシテの舞とが、お互いに、これら一連の情景を描写し合う様は圧巻です。
▼ 演目STORY PAPER:清経
演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。
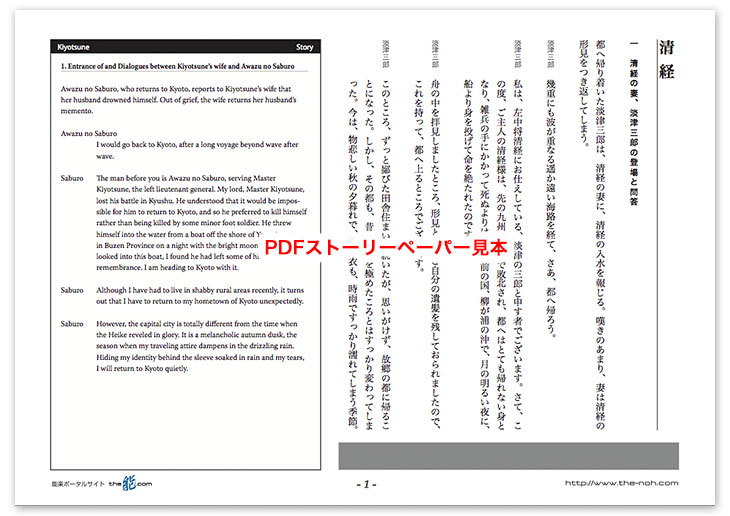
『日本古典文学大系40 謡曲集 上』横道萬里雄・表章 校注 岩波書店
『新潮日本古典集成 謡曲集 中』伊藤正義 校注 新潮社
『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂
演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。



 [ 清経:ストーリーPDF:584KB
[ 清経:ストーリーPDF:584KB