 |
 |
 |
| > Top > 支える人びと > 小林繁 |
|
|
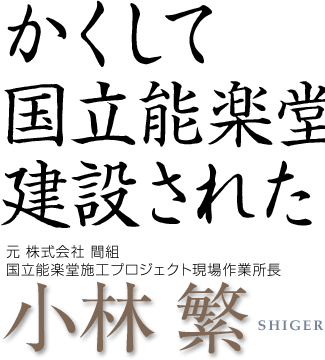 |
 |
撮影:大井成義 |
2008年、国立能楽堂(東京・千駄ヶ谷)では開場25周年を祝うさまざまな催しが行われた。そのひとつに「国立能楽堂」というタイトルのビデオ映像公開があった。国立能楽堂ができるまでを丹念に記録し、そこに駆使された先進の設計思想、技術の粋、そして厳選された素材を紹介していた。流儀を越えた比類なき能楽の拠点、国立能楽堂には、こんな秘密もあったのかと驚かされる内容であった。
国立能楽堂建設プロジェクトの内容をもっと知りたい。興味を膨らませた編集スタッフがさまざまにアプローチした結果、施工に携わった間・住友JV※の現場責任者であり、ビデオにも登場する小林繁氏(元・株式会社 間組)にお話を伺えることになった。
二度にわたって対面の機会を設けていただいた小林氏は、大変気さくなお人柄であった。建設素人の編集スタッフにもわかりやすく、懇切丁寧にレクチャーしてくださった。国立能楽堂の各所には、建設に携わった人たちのこれを限りの営みと思いが込められている。それがこの素晴らしい舞台の隅々にまで行き渡っていると、改めて教えていただいた。
※ 間・住友JV:株式会社間組と住友建設株式会社〔現・三井住友建設株式会社〕によるジョイントベンチャー(共同事業体)のこと。国立能楽堂施工プロジェクトの幹事会社は株式会社間組が務めた。
(本文の最後に、国立能楽堂の内部など貴重な写真を小林繁さんのコメントとともにお楽しみいただけるフォトツアーがあります)
初めての体験に戸惑いながら
 |
国立能楽堂全景 撮影:大井成義 |
「能楽堂、それも流儀を超えた唯一無比の国立能楽堂の施工現場に、作業所長として入ることになり、正直なところ、相当な戸惑いがありました」(小林氏・以下カギカッコ部分同)
小林繁氏は、プロジェクトに挑むことになった頃の心境を、率直にこう語った。城郭建築に携わったことはあったものの、能楽堂は初めて。父親が宝生流の謡を習っていたものの、自身は能と接点をもったことがない。しかも国家プロジェクトである。現場のリーダーになる責任の重さも更なる重圧となっていた。
「でも建築事業のトップの上司が『行ってこいよ』と激励しながら背中を押してくれて……。やってやろう、世界でひとつしかない建物を造ろうと、高い目標を掲げて取り組むことになったのです。東京・渋谷の松涛にある観世能楽堂を見学させてもらうなどして、知識を求める一方、心構え、気持ちを高めました」
国立能楽堂建設のプロジェクトがスタートしたのは、1976年(昭和51年)。設立準備調査会発足に始まる。1979年(昭和54年)には土地が購入される。管轄する建設省〔現・国土交通省〕の入札を経て、間・住友JVが受注した。明治神宮や会津・鶴ヶ城ほか寺社、城郭といった日本の伝統建築物の修復に力を揮ってきた間組にとっては、その実績が認められたかたちとなった。設計を担当したのは、現代建築のみならず、古建築の権威でもあった建築界の巨星、故・大江宏氏〔1913年〜1989年〕である。建設省、大江宏建築事務所、間・住友JVが手を携えて正式に起工したのは1980年5月であった。
一番気を使った檜の選定と取り扱い
 |
国立能楽堂舞台 撮影:大井成義 |
高い目標の実現へ向けて、まずこだわったのが素材である。演者が舞う本舞台、橋掛かりの床には極上の尾州檜を使った。樹齢400年、無節で板目、色合いの揃ったものを厳選し、さらにそのなかから選りすぐった。
「わずか数ミリに満たないヤニ壷〔ヤニのたまった筋のような箇所〕でもあれば、すぐにハネて、本当に確かな品質のものばかりを選び出しました。ここが一番苦労した作業だったとすらいえますね。当時、1リューベ〔1m3〕が1200万円ほどで、およそ5リューベ使用したと記録されていますから、舞台の床だけでも6000万円はかかっています。ハネたものを含めるとどれほどになったか。もちろんハネた品も他の施設で転用されたようですから無駄にはなっていません」
ほかの部分は予算を遙かに超えることから、国産材は断念せざるをえなかった。そこで、柱や梁、階(きざはし)、棰(たるき)、母屋(もや)、研修舞台などには、樹齢2000年を経た台湾檜が使われた。ちなみに約130リューベが供されたと記録されている。
「私自身が台湾に飛び、阿里山周辺の原生林にまで分け入って調査を敢行しました。さらには切り出した後の貯木場の状況確認、そして現地製材した木々の選定にまで立ち会いました。比べてみるとわかりますが、台湾檜の方が国産材よりも赤みがかっているという特徴があります。国産材に近い材質のものを選び出すのにも苦労しました」
施工の際の、檜の取り扱いにも細心の注意を払った。手の脂がついてしまうとそれだけで大きなダメージになる。作業者は手袋と足袋を着けて作業し、また見学者が間違っても素手で触らないよう徹底管理した。
「国家プロジェクトということで、建設省の方々、建築関係者、一般の方々まで全国から見学に来られました。有難いことでしたが、実は木に触らないかハラハラのし通しでしたね。舞台からはできるだけ遠ざけるよう、気を使いました」
能舞台の屋根は檜皮葺で、一部見所のそれは柿葺(こけらぶき)と、伝統建築ならではの竹の釘で止めていく技術が用いられている。
「檜皮と柿は丹後、丹波といった産地からのものですが、今はもうあれほどのものは揃わないでしょうね」
設計者の思想を理解し、実現に取り組む
 |
建設中に建築家の故 大江氏(前列右)を囲む関係者たち。 後列左から3番目が小林氏(提供:株式会社 間組) |
 |
建設中の様子(提供:株式会社 間組) |
国立能楽堂設計者の大江宏氏は、日光東照宮の修復や明治神宮宝物館の造営に携わった古建築の第一人者であった大江新太郎〔1876年〜1935年〕を父にもつ。近代建築の作品を生み出す一方で、日本の伝統建築のスタイルやデザインの活用にも積極的に取り組んだという。国立能楽堂の設計にあたっては『近代建築の良さと日本建築の伝統的な味を両様に享受し得る現代の日本人の感性に訴えかけるものを目指した』という。小林氏は大江氏と張り詰めた緊張関係のなかで、施工現場に大江氏の設計思想と手法を浸透させていくのに力を注いだ。
「大江先生のことを私たちは大先生(おおせんせい)とお呼びしていました。大先生は非常に霊性を大切にされる方で、木にも霊が宿るといったことをよくおっしゃっていました。また、能は古代的なアニミズムに通じているから、そういう特性に相応しい場を創り出すことが重要であると説いておられました。
いろいろな思い出がありますが、京都・西本願寺の能舞台を見にご一緒させていただいたことが忘れられません。国宝の貴重な舞台を先生の解説を伺いながら見ることができ、その上舞台にも上がらせてもらえたのですから。このほか京都ではもうひとつ舞台を拝見しました。また途中下車した名古屋で大先生を慕う錚々たる人たちが設けた会合にも参加させていただき、その偉大さを改めて実感しました」
大江氏の設計は非常に優美で、その美しい曲線は「大江流」と称されたという。
「たとえば屋根の下のラインは見た目でまっすぐでも、実際は両端はあがっているのです。日本の伝統建築の手法で少し両端が上向きに反るようにして、見た目でまっすぐに見えるようにするのです。こうした曲線をはじめ、大先生の描く曲線には独特の柔らかさがありました」
また通常の施工図は、躯体図から始めて徐々に細部をつめ、仕上げ図面に至るが、大江氏の設計ではまずアイデアのスケッチがもとにあり、そこから仕上げを見通して躯体図へ落とし込んでいくという逆向きのルートで作業が行われた。
「施工図のスタッフもずいぶん面食らったようです。5、6名ほどで交替しながら対応しました。躯体構造を絶対に動かすようなことはなく、仕上げに大江流を駆使し随所にイメージを作り上げていきました」
大江氏は数多くの取材のなかで、とかく窮屈なものと思われがちな能を、「できるだけ自由な雰囲気で観てもらえる柔らかいものを創るように努めたが、伝統芸能としての『格』は重視した」と繰り返し述べ、「観能に訪れた人を自然に能に引き込む導入への仕掛けも配慮した」とも語っている。さまざまな意図と意匠の追求がなされた国立能楽堂の施工は難事業であったはずだが、小林氏はこともなげにこう語る。
「苦労したのは材木の選定と施工図の描き起こしくらいで、あとは建設省(現・国土交通省)、大先生の一大プロジェクトに対する熱意を充分に汲みとり、温かみのある指導、協力でスムーズに施工しました」
現場に流れていた緊張感
 |
完成直後の国立能楽堂俯瞰写真(提供:株式会社 間組) |
小林氏の話を伺っていると、難事業を苦労とも感じさせなかったのは、現場に流れていた張りつめた緊張感のなせる業ではなかったか、と思えた。
「能舞台で演者が舞うときは、しわぶき(咳)ひとつ憚られます。それと同様の緊張感が確かに現場にはありました。木っ端ひとつ落とす音も憚られる感じがありました」
そういう現場の雰囲気づくりには質の高い職人の存在もあった。間・住友JVに集う施工スタッフは、小林氏の期待した高いプロ意識を持って業務に臨んでくれた。そのなかには、宮大工の匠たちの姿もあった。
「日本の伝統建築を取り入れるにあたって、宮大工の会社2社に木工事を担当してもらいました。舞台まわりは大阪の棟梁にお願いし、玄関からのアプローチ部分は名古屋の棟梁にやってもらいました。
一緒に仕事をして、宮大工の職人が非常に道具を大切にするところに強い印象を覚えましたね。特に鉋や鑿を研ぐ時間が長く、せっかちな人なら休んでいるんじゃないか、早くやればいいのに、と思うでしょう。でも彼らは研ぎ澄まされた道具の質の高さで技術の高さを示している。またそれぐらい研ぎ澄ました道具と技術をもたなければ、日本の優れた伝統建築を実現できないのです。日本の木組みはまさに芸術品。様式自体は中国伝来のものが多くありますが、それを洗練して匠の技にしてきたのは、我々の先祖、先人たちで、彼らはそれを受け継いでいるわけです」
“建築屋冥利に尽きる”
 |
1983年(昭和58年)9月には、国立能楽堂の記念切手も発行された (小林繁氏蔵) |
1983年(昭和58年)8月30日、起工式から約2年4カ月を経て、国立能楽堂が竣工した。小林氏が率いた現場のチームは160万時間以上を無災害で乗り切り、東京労働局から局長優良賞を受賞した。
「大先生の設計事務所、施工スタッフ、管理者である建設省、皆が和を重んじて連携し、現場でしっかり安全への意識を高めて取り組んだ結果です」
完成から2年後の1985年(昭和60年)10月。国立能楽堂は、優れた建築物の構築に携わった建築主・設計者・施工者の三者を表彰する建築業協会賞(BCS賞:Building Constructors Society Prize)の特別賞を受賞した。国立能楽堂は、建築のプロたちから見ても、やはり特別な存在だったのである。
「このような歴史に残る建築物を手がけられるのは、建築業界でもほんの一握りです。間組からの施工スタッフも図面担当を入れて20名に満たないくらい。一生に一度といってよいプロジェクトに参加できたことは本当に幸運でした。建築屋冥利に尽きると思っています。関係者全員、同じ思いでしょう」
時間は前後するが1983年9月15日の開場式典では、観世元正、宝生英雄、喜多実という当時の三宗家による「翁」の「弓矢立合」で舞台披キが行われた。その後、流儀を問わない演能の拠点として、能楽師の研修育成の場として、豊富な資料による学習・研究の場として、能楽にまつわる物品の展示場として、さまざまな活動が花開いていった。小林氏も折にふれ、観能に足を運ぶという。
「アクションのあるものが好きで、まずは「道成寺」がお気に入りです。そして勇壮な修羅物、たとえば「八島/屋島」なんかもいいですね」
観能で目にするのは能ばかりではない。舞台上のことも、それ以外も何かしら気にかかる。
「今も檜の香りがするでしょう?」確かめるように尋ねる小林氏の面差しに、手塩にかけたわが子を気にかける慈父の表情を見た。(2009年8月21日)
小林繁 プロフィール
1939年東京に生まれる。1962年、日本大学理工学部卒業後、株式会社間組へ入社。主に首都圏で建築現場や工事管理部門に勤務した後、1980〜1982年、国立能楽堂建設工事で所長を務めた。1985年、横浜支店建築部長。1987年、同支店営業部長。1991年、横浜支店長。1993年、取締役就任。1995年、建築統括本部副本部長。1999年、取締役退任。
一口メモ:株式会社間組では毎年催される明治神宮薪能に協賛し、舞台設営も手がけています。
今回のインタビューに併せて、普段は一般公開されていない楽屋や鏡の間など、国立能楽堂の貴重な写真を公開します。小林繁さんのコメントとともにお楽しみください。

|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2025
CaliberCast, Ltd All right reserved.