 |
 |
 |
| > Top > ESSAY「わたしと能」> 有吉玉青 |
|
|
幼い頃から能に接していたり、あるいは大人になってから能に魅せられたり、と、十人十色の能とのご縁。
さまざまなジャンルの著名人たちが能との関わりや魅力を綴るエッセイ「わたしと能」。
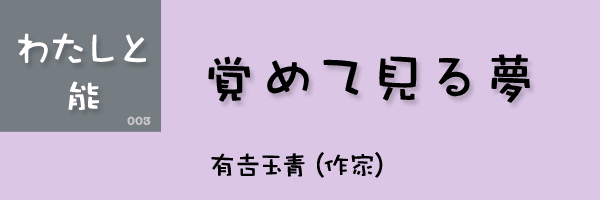
 |
絵:タケウマ |
能に行くと眠くなる、と言う人がいる。動きがなくて退屈だから寝てしまう、とも。でも、気持ちがよくて、ついうとうととまどろんでしまう、ということもあるだろう。寝るのは一生懸命やっている人たちに申し訳ないが、気持ちがよくて寝るならば、必ずしも失礼ばかりではないような。
というのは言い訳だろうか。というのは私もよく、寝てしまうんです。もっと正確に言うならば、寝たのかさえもよくわからない。気がつくと、さっきまで舞台の真ん中にいたはずのシテが、目付柱のところにいたり、橋掛かりにいたりする。
今回もそうだった。演目は「善知鳥(うとう)」。猟師が生前の殺生の罪により、死んでなお生き物の命を奪ったことを嘆き、地獄の化鳥に苛まれるという話である。
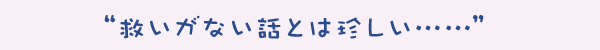
たいてい亡霊は僧によって慰められ折伏されて成仏するから、救いがない話とは珍しいと、興味を持って出かけた、はずなのだが。
前半、僧が死んだ猟師の妻子の前で、故人が狩猟に用いた蓑と笠を舞台に置いた。そうして、拝んでいるなあ、これは蓑と笠を霊牌に見立てて拝んでいるのだなあと思って、ふと気づくと、それらはもう舞台の端に置かれていた。
猟師の亡霊が舞っていて、囃子が激しい。なるほど、これが解説に書いてあった「カケリ」というもので、猟師が善知鳥の雛を狩る場面。シテの演技と囃子がかけあうところだな。ここは見せ場だ、よく観よう、と思ったものの、これはたぶん事前の打ち合わせはしても、ほとんど即興でシテと囃子が対決する、一種のジャズだと感心したあたりから、再び記憶がとんでしまった。気がつくと猟師は橋掛かりを揚幕の方へと音もなく歩いていたのである。なんてことだ、もう終わりじゃないか。やはり、寝ていたのだろうか。
いや、寝てはいない。私は確かに妻の表情を覚えている。地謡座の前で片膝を立て、夫の亡霊が死してなお苦しんでいる様をずっと見ていた、耐えていた。自分たちを養うために生き物を殺すことを生業とした夫が、その罪に問われているのだ。表情を変えないはずの能面が、わずかに震えているように見えた。

私はまた、人間が生きるということの難しさを考えてもいた。生きるためには食べなくてはならず、生き物の命も奪う。人間は皆、生まれながらに罪人である。
ただ、台湾で、「素食」というものを食したことがあった。不殺生の教えを守り、動物性の材料をいっさい使わない食事である。工夫をして肉や魚の味や食感を見事に再現しているものもあって面白く、また、そうまでしても食べたいのだなあと、かえって人間の煩悩の強さを考えさせられた、そんなことも思い出した。
猟師は生前、雛を狩ったために、死して地獄で親鳥の善知鳥の化鳥に責め苛まれる。彼は亡霊となって子供に会おうとするも、阻まれる。親と子——そのあたりからだろうか、こんな記憶も蘇ってきた。
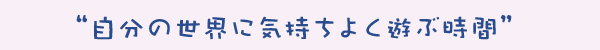
私は小学校のころ、謡を習っていた。母が鼓を習いはじめ、私も興味を持ったが、まだ鼓は重く、持てるようになるまで謡をやることになったのだ。ところが謡の本の字が読めない。そこで祖母が筆で、子供の読める文字で書き直してくれた。私は祖母の手製の謡本で、「熊野(ゆや)」や「紅葉狩」を意味もわからず唸り、母がそれに合わせて鼓を打った。
素食のこと、謡のこと、ふだん思い出さないことを、能を観ながら思い出していた。あるいは夢を見ていたのだろうか。
と言ってもそれは、そこで寝たから見られた夢だったに違いなく、いややはり起きていて、能を観ながら見ていた夢なのではないか。
能のような極限までそぎ落とされた動きを前にして、自分の中にかえって何かがふくらむことはある。それは必ずしも目の前で行なわれていることと直接関係のあることでなくてもいいのではないか。能の時間は、自分の世界に気持ちよく遊ぶ時間である。
(2008年7月)
 |
有吉玉青 プロフィール 1963年東京生まれ、作家。早稲田大学哲学科、東京大学美学藝術学科卒。ニューヨーク大学大学院演劇学科修了。主な著書に『身がわり』 |
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2025
CaliberCast, Ltd All right reserved.