 |
 |
 |
| > Top > ESSAY「わたしと能」> 駒沢敏器 |
|
|
幼い頃から能に接していたり、あるいは大人になってから能に魅せられたり、と、十人十色の能とのご縁。
さまざまなジャンルの著名人たちが能との関わりや魅力を綴るエッセイ「わたしと能」。
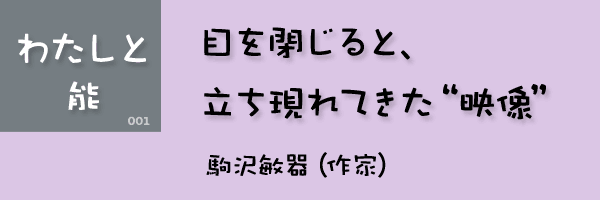
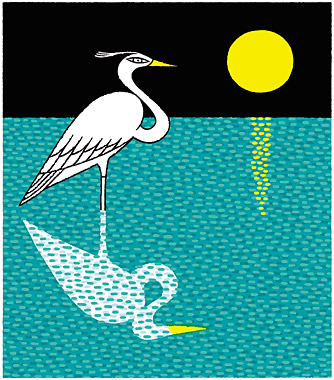 |
絵:タケウマ |
誘いを受けて、初めて能を鑑賞した。場所は国立能楽堂、高野山の声明に始まって「柿山伏」の狂言へと続き、お能は観世流による「鵜飼」という演目だった。まったく厭きることなく最後まで楽しく観劇できたのは、それぞれの内容がわかりやすく、初心者に向いていたからだろう。
まず声明に関しては、僕はいくつかのCDを持っているので、すんなりと聴き入ることができた。そのCDとは、奈良は東大寺の「お水取り」。同じく奈良の薬師寺で録音された「称名悔過(しょうみょうけか)」。そして高野山金剛峰寺奥の院で執り行われた「月並御影供(つきなみみえく)」。仏教に深い縁のない自分がなぜこんなものを持っているかというと、「声楽」としての読経に、大きな興味があったからだった。
お経に書かれた言葉そのものに“力”がある上に、その力を声に乗せて顕現させる声明は、ただそれだけで音楽として美しい。それを能楽堂において生で耳にすることになり、ひとりひとりの声や和音の響き、節回しの奥などに懐かしいものを感じた。どこが懐かしいかは後に置くとして、次は狂言の「柿山伏」。
これは説明するまでもなく、修行を終えて山から降りてきた山伏が、腹を空かせてひと様の柿を盗み食いするという滑稽譚だ。食欲を抑えることができず、あまつさえひとの物に手を出す山伏の修行とは、いったい何だったのだろうかと庶民の笑いを誘う。荘厳な声明の後での長閑な昔話には、外国からの観客も素直に笑いを見せていた。
休憩をはさんで能の「鵜飼」に見入る。安房の地から修行の旅に出た僧侶がふたり、甲州の地において、里人に1泊を願い出ることから話は始まる。しかし僧侶とて旅人に宿を貸すのは禁制だと断られ、ふたりは石和川のほとりに残る御堂を勧められる。しかしそこでは“光る物”が出るとのことで、僧は法力をもってそれを鎮めると決意する。

しかして夜半にその幽霊は現れ、殺傷禁断の地で鵜飼をおこなった罪で地獄に落とされた無念を、ふたりの僧侶にせつせつと聞かせる。地獄とはいかなる場所か、迷い定まらぬ霊の苦しみとはいかほどのものか、その辛さが胸に迫ってくる。ここで初心者が感じたものは、遠く室町時代にあっては「死」は間近なものであり、辺りいたるところに死を具現するものが、朽ち果てるようにころがっていたのだろうということだ。
そのさまを見ては地獄を想像し、死後そこにだけは行きたくないと、庶民たちは震えていただろう。それをふたりの僧侶が、ようやく法華経の念仏によって救うことになり、その効力を庶民はすがるような思いで見ていたはずだ。
声明からこの能にいたるまで、一貫して楽しめたのは“間”の妙であり、間を生み出している笛や太鼓のリズムだった。この“間”こそ、この世とあの世をつなぐひとつの合図でもあり力でもあり、そこに空いた穴のような場所を、魂が行き交うのを感じた。それを僕はとても“懐かしい”ことだと思ったのだが、それは日本の自然が持つ風情が、子供のときから耳を通して身についていたからかもしれない。
アメリカやカナダの国立公園で、僕は長い期間キャンプをした体験を持っている。スケールはもちろん日本とは比べ物にはならず、山容ひとつとっても美しさに恵まれたものが多い。そんなキャンプ地へ野生のエルクや白頭鷲が訪れるのだと言うと、誰もが憧れと羨望を目に浮かべるのだが、正直に言って僕はこういった場所でのキャンプには、途中で厭きてしまった。日本の山や森にある奥深さや、それこそ“幽玄”といったものが、まったく感じられないからだった。
日本では車で入って行ける場所でも、そこが相応に山深い地であるならば、日没と同時にあたりは不思議な空気に包まれ始める。ひっそりとした森の霊気、動きのない音、闇の先はまさにあの世ともつながってあるようで、夜半ともなると森の奥から鵺(ヌエ)の鳴く恐ろしい声が聞こえる。

このようなとき、生と死は近くにあってひとつなのだという想いが、深く考えるまでもなく、自然と胸に上がってくる。あるいはそのような想いを抱かせる力が、日本の自然にはもともとあるということだろう。この情緒の力を借りて森の夜を過ごすとき、僕は子供のころからどこかで“無常”を感じていた自分とつながる。
日本人の心や、日本の自然にあるものを奥から引き出し、型として高度に抽象化させたものが能だと僕は感じた。そして上演の途中、何度か目を閉じて、音やリズムや間に聴き入った。それらの重なりの奥から、やがてはっきりと“映像”が立ち現れてくるのを覚えたからである。目のまえにあるものよりも、目の内にあるものの方が、能ではないかと思ったほどだった。
(2008年5月)
 |
駒沢敏器 プロフィール 1961年東京生まれ。雑誌「SWITCH」編集部を経て、作家・翻訳者。小説に『夜はもう明けている』、紀行に『語るに足る、ささやかな人生』、『地球を抱いて眠る』、翻訳に『トーテム・サーモン—聖なる生命サーモンのおしえ』などがある他、長編小説『ボイジャーに伝えて』が近日刊行予定。本稿は“生のなかにある死”をテーマとする氏がかねて興味を抱いていた能に初めてふれた観能記。 |
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.