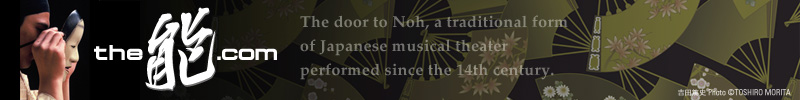
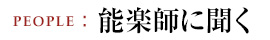 Noh Talk
Noh Talk
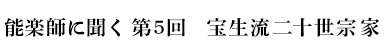



2018年、宗家継承10周年の節目を迎えられた宝生流二十世宗家、宝生和英氏の元を訪ねた。
22歳で流派を率いる立場となられた宗家が、変わらずもちつづける信念と経営者的視点。ロジカルなお考えをうかがうと、目からウロコが落ちることの連続だった。
能楽界に新風を吹き込む宗家のチャレンジ精神に、能の限りない可能性が感じられた。
![]() 第1部 能をマネジメントする
第1部 能をマネジメントする
2019年4月 聞き手:大島衣恵(喜多流能楽師) 写真:大井成義
第1部 能をマネジメントする
宗家継承10周年を経て
大島 宝生流の宗家を継がれて10周年を迎えられましたね。ご苦労もおありだったと思いますが、同時にやりがいも感じておいでかと思います。節目にあたり、ご自身の中で変化したと思うこと、また、変わらない点についてお聞かせください。
宝生 まず、家元継承時は22歳だったんですが、その時、私の恩師である佐野
最初の5年間は本当に家元業をたいしてしてないんですよ。今にして思えば、家元見習いの間にいろいろな事にチャレンジし、失敗したことで物事を俯瞰して見ることができるようになりました。
すると、5年目ぐらいから家元として仕事を任せていただけるケースが増えました。恐らく先生もそれを見越して仰ったのかなと思います。宝生会としての公人の動きに個の失敗を活かすことができました。そのあたりからでしょうか、私のスタイルが確立したのは。私の中では、半分能楽師で、半分がマネージャーなんですね。使い分けることは私にしかできないものだと思って取り組んでおります。こうした根っこができてからバランスを模索し、軌道にのってきたのは30歳を超えてからでした。
大島 そうでしたか。
宝生 変わらないのは「チャレンジすること」です。私は、能楽師としてではなく社会人としての下積みを経験しました。たとえば、雑誌の編集、デザイン、制作業務などありとあらゆる事務作業に1年間ほど携わらせてもらっていました。最近ですとセールスですね。まだまだひよっこですが、営業の仕事なんかも始めたりして。
すると、企業が何を求めているのか、読者に対して何を伝えるかを考えるようになります。辛口なご指摘をいただいたりもしましたが、何事もとりあえず1回はチャレンジしてみようと思っていました。なので今はハードルが高い舞台でも、プラスになることはすべてチャレンジしていますね。
変化したところとしては、誰のために何をするのかをしっかりと考えるようになったところです。我々はプロフェッショナルなので、ちゃんと提供する相手のことを見なければなりません。求道者的な立ち位置ばかりになると、プレイヤーとしては正しいかもしれませんが、社会の中に入る余地がなくなってしまうんですね。
大島 なるほど。組織を経営していく長としての視点と意識をお持ちなのですね。新しいことへのチャレンジや、社会の中での能の役割などを常に考えていらっしゃる。目標や目的を明確にお持ちの印象がございますが、それは培ってこられたものですか?
宝生 性格ですね。私自身はもともと大変な飽き性なんです(笑)。舞台に集中すると他はどうでもよくなってしまったりと、ひとつのものを突き詰めていると他のことを忘れてしまう。そこで、目標を定めることをひとつの指針にしようと決めました。自身をセルフマネジメントするために、目標を定めるスタイルになったということですね。
大島 若い人達がちょっと迷ったり悩んだりした時のヒントになるようなお話ですね。人は長所と短所が表裏一体。それを自分で理解しておくことは難しいことです。お立場上考えていかなければならなかったにせよ、お若いうちに自身の心がけ次第だと思われたのですね。

宝生流二十世宗家 宝生和英

喜多流能楽師 大島衣恵
観能は頭の洗濯。能の新たな活用法
大島 これから能を観てみようという方や、よく分からないと思っている方に向けて、能の魅力や面白さを教えてください。
宝生 能楽が面白いと感じはじめたのは20代後半からです。後見に座るケースが多いですが、その時、後見の仕事の他にいろんなことを考えたりしています。実は私、好きな場所がディズニーランドというエンターテインメント大好き人間なんです。エンターテインメントに触れると別の頭になる時があるんですね。お能でも別の頭に切り換えられると考えた時、能楽とは時間を有意義に使える一種の“方法”だと思いました。
ある時、客席でずっとものを書いていらっしゃる人がいました。その方にお話を伺う機会があり「何をしていらっしゃるのですか?」とたずねたら、「自分はデザイナーで、能については興味がなく舞台もわからないが、なぜかここに来るとアイデアが浮かびラフが描ける。そのために能楽堂に来ている」と仰る。他にも、あるライターさんは物語を考える時間にお使いで、観劇しながら脈絡なく浮かぶ単語を紡ぐと最後は1本の物語になるそうです。以前、いとうせいこうさんとお話している時に言われた「能はまさに夢を見ているようなものだよね」というひと言は的を射ていると思います。
大島 ええ、確かに。
宝生 オムニバスでいろんな発想を浮かべ、それを自身でブレストした上でひとつのパズルを完成させるという工程を行っているんですね。能とは、自身をブレストできる、また頭を洗濯できる空間に使える、というのが私の持論になりました。
最近は「白洲正子シンドローム」という言葉を使っています。50代、60代以降の方々は、能を高尚な芸能として見てくださっているから、公演時に能楽以外について考えるなんて失礼だと思われる。そういう方々はご自身ですでに能の楽しみ方をお持ちなので、私が改めて何か提案する必要はありません。ただ、白洲正子さんが提唱していた能楽の価値が絶対の正解ではないと考えていて、ブレストや意見出しという機会が多い30代、40代の人達に、今の時代とフィットするような鑑賞方法を提案していきたいんです。よく「日本人だったら伝統芸能の能ぐらい見ておかないと」という意見も聞かれますが、私はあえて声高に言う必要はないと思っています。
大島 なるほど。白洲正子さんの本を読んで能楽堂に来たという方に私自身何人もお会いしてますから、影響力はあると思いますが…。
宝生 インフルエンサーの時代ですよね。三島由紀夫、黒澤明、あとドナルド・キーンさんにしても。今みたいに情報が多くない時代は、インフルエンサーが出した本や新聞を見て文化に触れ合うという方法が全盛の時ですよね。
大島 そうですね。能楽に興味をもっていただく入口に白洲さんというのはあると思いますね。いろんな見方で能が楽しめるというお考えには共感します。ある解説者の方が、「隅田川」ではシテの母と子どもを通して親しい人との別れなどを想う…舞台を観ながら個に思いを馳せられるのが能の特徴じゃないかと仰っていました。「さまざまな思いや考えを巡らせながら舞台を観たっていいんですよ」と提示することで、伝統芸能だと構えてしまう方に「あぁ、それでもいいんだ」と思っていただけるような気がしますね。
能楽でメンタルトレーニング
宝生 将来、伝統文化はカテゴリーを2つに分けなきゃいけないなと思っています。能、文楽、歌舞伎、雅楽が並列ではダメなんですね。歌舞伎と能楽ではそもそもゴールが違うことを理解しなければいけない。ゴールが違うところと一緒にやっても結局バラバラになってしまうんです。日本では伝統文化を横並びにさせる傾向があって、公演しても残念なことに「何がしたかったの?」で終わってしまうことが多いんです。伝統文化A、Bと分けなければ文化の多様性が失われてしまうと危惧しています。このままだと、よりエンターテインメント性が強まったもの勝ちの市場になってしまう…。
心を大きく揺さぶるのがエンターテインメントだと言えますが、我々能の世界は、メンタルをフラットな状態にする非常に希有な芸能です。そして、些細なことでも動じない心をつくるのは、ある意味トレーニングです。エンターテインメントとメンタルトレーニングとしての文化。この両者があることによって文化の多様性が保たれると思っています。残念ながら、今はエンターテインメントが注目される多数派が正義という時代。ポピュリズム自体について、私は対抗すべきなのかなと思っております。
大島 確かに、能にはメンタルトレーニング的な側面があることは忘れてはいけませんね。だからこそ戦国武将達も稽古し、愛好していたのだと思います。
宝生 日本の高度経済成長を支えたもののひとつとして、能楽があると思います。というのも、激動の時代こそ冷静に物事を判断したり、リスクがあっても動じないメンタルが必要となる。嗜むことで日頃からそれを心がけられるのが能楽です。今は周りの大国に影響され過ぎて洗濯機の中をグルグル回されちゃっているような気がします。
たとえ予想外のことが起こっても、冷静に対処をすればきっと何とかなるんですよね。それができない理由は、エンターテインメント市場や西洋文化に寄ってしまったところにあるのかなと思っています。

大島 家元のプロフィールに裏千家淡交会 東京第一東支部 支部顧問とありました。私も少しお稽古をつけてもらうことがございますが、今のお話をうかがって、お茶を嗜む際の心持ちと共通点があるなと思いました。
宝生 アートマネジメントが違うだけで、茶道と能は似ていると思います。
裏千家の顧問は、お声がけいただいたものですが、根本には目的が一緒であれば組めるという持論がありましたのでお請けしました。
舞台芸術は、だいたいがB to Cを目指します。提供者がいて、お客さまがいて、お客さまからのチケット収入と物販収入で我々は収益をあげて次に回していくというスキームです。なかなか能楽が苦手とするところですが、B to Bには強い。つまり、ビジネスパーソン同士を繋いだり人材育成に貢献するとかですね。同じような方向でやっているのが茶道だと思っていて、B to Cももちろん大事ですが、B to Bの懐でもしっかりと運営基盤を築くことができる。そこで我々が学ぶところも多いんじゃないかと思います。
舞台は実験の場。増えていった自身の“引き出し”
大島 では、少し能楽師側の質問です。ご自身の芸を磨くということもさることながら、指導者という立場もおありですね。ご自身が舞台に臨む際やお稽古をつける際に心がけていることはございますか?
宝生 ちょっと感覚を能楽師に戻しましょう(笑)。
両方をいっぺんにこなせるほど私は器用な人間ではないので、能楽師をやる上では優先順位をつけるようにしています。今一番優先しているのは自身の鍛錬です。分かっていない人間が偉そうにああしろこうしろと言ってしまっては逆効果な指導になってしまいます。決まり事というのは、先代から受け継いでこられた方に教えてもらうことが大事なので、そこは先生方にご協力いただいています。私も一緒に教えてもらった上で、将来的な指導に繋がればと考えています。
私はかつて、最大で5人の先生に同時に習うということがありました。先ほどお名前が出た佐野萌先生、三川泉先生、今井泰男先生、あと芸大の先生も何人かいらっしゃいます。一週間のうち、だいたい4日か5日は稽古になる。すると日によって先生から言われることが変わるんですよね。それに合わせて毎回変えなければいけなかったので、「この先生はこれをやると怒るからこうしなきゃ」と考えるクセがつくんです。次第にそれが楽しくなってきて、どこまでが怒られないだろうとか、これは注意されるかなとか、ギリギリを狙うような稽古になっていきました。
大島 それは面白いですね(笑)。でも、なんとなく分かるような気がします。

宝生 すると、引き出しが増えるんですね。迷った時や曲によって切り替えできるようになり、今とても助かっています。なので、いろんな人の話を聞いて、とにかく引き出しにしまうことを大事にしていますね。
私、とにかく最初は否定されることからスタートしているんですよ。「君はダメだから」とか「本当に今、能楽界の中で一番下手だから」とか言われて(笑)。「この人に褒められるためにはどうしたらいいんだろう」とか「見返すためには納得させられるだけの舞台をやらなきゃいけない」という反骨精神こそが原動力でした。ただ、一人の人間と真摯に向き合っていくうちに、その人の裏の意図まで汲むことを大事にするようになったんです。「あぁ、そうか、この先生は型が大きい小さいの話じゃなくて、ここの軸を大事にしなきゃダメだと言いたいんだ」とか。
一回一回の舞台が実験の場です。今まではこの先生の方針でやっていたけれど、こちらの先生の方針でやったらどうなるんだろうといったことは、本来稽古会などで試してみるものだと思いますが、私の場合はたまたま公演数が多いので、実践しつつ試行錯誤する時があります。稽古会は、ただただお能を覚えるのではなく、ちょっと遊ぶ“ゆとり”が大事なのかもしれません。
大島 私の場合は、基本的には父と亡くなった祖父がいました。仰る通り、父、祖父で言うことが違うということはございましたね。ただ、宗家のように最大5人というのはなかなか…。
宝生 ええ。しかも、親からまったく稽古を受けていないのがなおさら良かったんですよね。
大島 そういえば、十四世・喜多六平太先生(1874-1971年)も幼少期に家元になられて、弟子筋の先輩方から教えをうけて名人になられた…。いろんな方の教えをうけられるということはつまり、それだけ周りが期待をかけている、ということではないでしょうか。
宝生 「弟子家」という考え方が少し難しいんですよね。私の中では、この業界はボトムトップなんです。底辺が広くないと上に一切利益はこない。家元が儲かっていても、下が細っていったら何も上がってはこないんですね。我々のハッピーとは、それぞれの能楽師達がハッピーになることとイコールなんです。だから、家元が何かやることによって下の人達が動きやすくなり、お弟子さんが増えて収入が増える、そこから例えば免状料(演目を演じるために必要な免許料のこと)がまかなえるならば家元もハッピー…というスキームが理想です。
下の人達が家元を妬むことと、家元が必要以上の欲を出すこと、この2つが最も怖いことだと考えています。あまり情報出さない家元の方も多いのですが、そうすると変に勘ぐられてしまうことがあるんですね。財を貯めてるんじゃないかとか…。勘ぐられるというのは一番よくない。お金は貯めるものではなく回してなんぼなので、目に見える形で還元する。飲み食いに使うのではなく、企画やイベントにチャレンジする時は実費でやってみるとか、そういう関係がいいですね。
大島 風通し良くありたいという感覚を持っておられることが、まさに今求められているリーダー像という印象を受けました。下の人達が動きやすく、という考え方は経営者感覚ですものね。
宝生 家元が動くことでライン引きできることもあります。例えばですが、地方同士でぶつかることがあっても、「家元が言うなら」と納得してもらえる。家元にしかできないことって結構多いので、「家元だからしょうがない」を有効的に使わないといけないんですよね。一番無駄なのは家元になるために仕事をすることです。(第1部 終/第2部へ続く)![]()
第2部 これから能が生き残るために ▶
宝生流二十世宗家 宝生和英(ほうしょう かずふさ)
1986年、室町時代より続く能楽の名門、宝生家に生まれる。1991年「西王母」子方で初舞台。2008年、東京藝術大学音楽学部邦楽科を卒業後、同年4月に宗家を継承。10月には、自身の能楽に対する想いに賛同した有志達と「和の会」を発足し、2018年にグランドフィナーレを迎えるまで主宰した。伝統的な演出に重きをおく一方で、異業種とのコラボレーション企画などに取り組み、能楽の新たな価値の創造を模索するためマネジメント・経営業務も精力的に行う。国内はもちろん、イタリアを中心とした海外文化活動にも力を入れている。
インタビュアー:喜多流能楽師 大島衣恵(おおしま きぬえ)
喜多流シテ方。能楽協会会員。エリザベト音楽大学非常勤講師。1974年、東京生まれ。2歳の時に広島県福山市へ転居。同年、「鞍馬天狗」の稚児で初舞台。祖父久見(能大島家三代目)、父政允(四代目)に師事。1998年より、喜多流では初の女性能楽師として舞台活動を行う。以降、海外公演にも参加し、2010年財団法人広島国際文化財団より「国際交流奨励賞」、2018年ひろしま文化振興財団より広島文化賞受賞。


