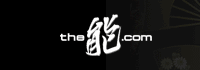 |
 |
 |
| > Top > ESSAY 安田登の「能を旅する」第4回 |
|
|
亡霊や精霊である“シテ”と 出会うところから始まります――。
連載「ワキから見る能の世界」では、
舞台でワキ方として活躍されている安田登氏に、
旅人・“ワキ”の目線から見た、能の世界を語っていただきます。
なぜ芭蕉たちは那須で20日も費やしたのか
荒涼たる那須野の原で、幻想の能世界に迷い込んでしまった芭蕉たち。やっとの思いでそこを抜け、土地の城代家老である図書(ずしょ:浄法寺高勝)の家に落ち着いて、しばらくの間、旅をお休みします。
約20日の間、図書(ずしょ)やその弟の家を中心に、芭蕉たちは那須周辺をあっちに呼ばれては句会を催し、こっちに呼ばれては宴会などしたり(ってこれは想像)して過ごします。ちなみにこの那須での旅程は、芭蕉たちの足ならば2日か3日もあれば充分。それなのになぜ20日も費やしたのか。
それは、この期間が「中有(ちゅうう=中陰)」の期間だからなのです。
深川から日光への旅で、かつての自分を捨てる、すなわち「死」の体験をした芭蕉たちは、次の再生までの間、長い長い「中有」の道を歩きます。
仏教では亡くなって仏様になるまで(あるいは生まれ変わるまで)の49日間、中有の道を旅します。三途の川では奪衣婆に衣を剥ぎ取られたり、閻魔大王に会っては生前の罪を問われたりと、なかなか大変な旅です。
その道は水平な道ではなく垂直の道。どんなに歩いても進まない。空間としてはここに留まっていながらの「時間の旅」。芭蕉たちの那須周辺の旅も、中有の道と同じく垂直の道のりであり、ワグナーの『パルジファル』でいうような「時間が空間」の旅なのです。
同じところをぐるぐる回っている芭蕉の動きは、まるで能の舞のようでもあります。能の舞も舞台上をぐるぐると回ります。ぐるぐる回ることによって変容が起きるのです。
だから芭蕉たちも次の再生のフェイズ(白河から始まる)までのしばらくの間を、ここ那須の中をぐるぐる回りながら中有の旅を続け、その身を変容させていったのです。
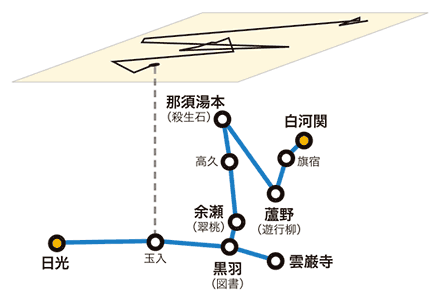
不気味な石の上に、鳥や蜂、蝶がバタバタと落ちて死んでいく…
が、もとより諸国一見、一所不住の身、いつまでもこうしちゃいられない。
再び旅立った彼らが最初に訪れるのは、これまた能に因んだ名所「殺生石」です。狐の悪霊が石となったという怖い歌枕。
能『殺生石』のワキは、珍しく名のある僧。玄翁(げんのう)です。あの、トンカチみたいなやつを「げんのう」っていうでしょ。玄翁和尚がトンカチ(金槌)で狐の悪霊を退治したからと、その名の由来になった玄翁和尚です。
さて、玄翁和尚が従者と旅をしていると、空飛ぶ鳥がバタバタと落ちていく。よく見ると、その下には不気味な石。不思議に思った玄翁がその石に近づこうとすると、どこからともなく女性が現れて「その石には近づき召さるな」という。
女性がいうには、その石は昔、鳥羽院の時にいた美女、玉藻の前の精魂が凝り固まったものだとのこと。玉藻の前といえば文学・音楽・教養なんでも一流という才色兼備の絶世の美女。ただ、ちょっと問題がある。実は彼女、狐の精魂。しかも不死。その国の王を誑(たぶら)かして、国をつぶすのを趣味とする。最初はインドで王国を崩壊させ、次に中国で帝国を傾け、今度は日本を!とやって来たのです。
「え、でも、それってすごい昔の話でしょ。しかも、ここは都からは遠く離れた那須でしょ」と驚く玄翁に彼女は詳しく語ります。
…って、ここら辺の話は本サイトの演目紹介の『殺生石』にあるので省略しますが、そんな殺生石に芭蕉たちは立ち寄ったのです。芭蕉が訪れた当時でも、石の毒気はいまだ滅びず、蜂や蝶が地面が見えなくなるほど重なって死んでいたそうです。
怖い…。
 |
© paylessimages - Fotolia.com |
「殺生石」から「清水ながるゝの柳」へ
さすがに現代の「殺生石」に毒気はないし、蜂や蝶が地面が見えなくなるほど重なって死んでもいません。が、たくさんの白い石の中に、赤いよだれかけをかけたお地蔵さんの群列。そして硫黄の湯気がところどころに噴出すさまは、まるで死の国にさ迷いこんでしまったかのような錯覚すら覚えます。
現代でもそうなんですから、まだ毒気が残っていた芭蕉の時代の殺生石ってすごかったんでしょうね。
そんな殺生石を一見したあと芭蕉たちは、いよいよ念願の「遊行柳」に向かいます。『おくのほそ道』前半の旅の中で、芭蕉がもっとも寄りたかった名所のひとつ。西行ゆかりの柳です。
殺生石から遊行柳までの道は県道が通っていますが、できるだけそういう大きい道を避けて歩こうとすると、いまでもちょっと不思議な感じがして、ここが現代の日本であることを忘れそうになります。殺生石の毒気にあてられたまま車の道を避けながら遊行柳に向かう。
やがて田の中に柳が見えてきます。
この柳を芭蕉は「清水ながるゝの柳」と呼んでいます。西行の歌からつけた名前ですね。正確な意味では歌枕ではない。が、もうこれは完全に歌枕に準ずる扱い、というか、歌枕以上の扱いを受けている名所です。
「清水ながるゝの柳」と呼ばれる由来となる西行の歌です。
道の辺に 清水流るる 柳陰
しばしとてこそ 立ち止まりつれ 西行
芭蕉はこの柳の蔭に立ち寄った時のことを「今日この柳のかげにこそ立ち寄りはべりつれ」と書いています。「立ち寄りはべりつれ」という言葉は、西行の「立ち止まりつれ」をパロディすることによる西行へのオマージュですね。
そこで一句。
田一枚植えて 立去る 柳かな
田一枚を植えたのは誰か、立ち去ったのは誰か
能のワキも歌枕などでは歌を詠ったり、古歌を詠じたりします。そこに草木などの自然物があれば、それに向かって詠うことが多い。
と、能では必ずといっていいほど「のう、のう」とシテに呼びかけられ、だんだん異界に誘い込まれていくのです。
西行ゆかりの「清水ながるゝの柳」に向かって詠いかけた芭蕉、当然ここで「のう、のう」を期待していたのかも…と思いきや、実はこの句の中にすでに「のう、のう」が含まれているのです。
「田一枚植えて 立去る 柳かな」の句は、大変論争の多い句です。
議論の争点は、田一枚を植えたのは誰か、そして立ち去ったのは誰かというところ。
これが「田一枚植えて立ち去る〈乙女〉かな」だったら問題でも何でもない。田を植えるのも乙女だし、立ち去るのも乙女。
で、これと同じように読むと〈柳〉が田を植えて、立ち去るとなる。
でも「そんなことあるわけないじゃん」と思うので論争になる。が、これは近代人の悲しさ。
前にも書いたように日本人は目に見えないものも見ることができる。能は日本人のそのような能力に期待するから舞台上に大道具も置かないし、照明も使わない。
ましてや芭蕉は詩人。見えないわけがない。となれば、芭蕉の目に見えた、幻想の柳の精が田を植え、そして立ち去ったと読むのが普通ではないかと思うのです。
 |
© Paylessimages - Fotolia.com |
西行の霊、西行の詩魂でもある「柳の精」
芭蕉は、「清水ながるゝの柳」に「しばしとてこそ」立ち止まった。ここは西行や、能『遊行柳』のゆかりの地。
畔に座って柳を眺めているうちに芭蕉は思わず、能『遊行柳』の謡を口ずさむ。口ずさんでいるうちに眠くなり、半覚半睡状態になる。
すると、そこに能のシテである老人の柳の精が現れるのです。この柳の精は、西行の霊でもあり、西行の詩魂でもあります。
柳色の装束を着た精霊が幻影の中でゆるゆると舞ううちに、土色の田が緑に変わっていく。もちろん実際に田を植えているのは早乙女かも知れない。でも、その姿は背景となり、芭蕉の「もうひとつの目」に映った能のシテが田の上を舞っているのです。
能の柳の精霊は、僧の「御法(みのり)」に感謝して舞台から立ち去りますが、芭蕉の幻影のシテは、田を自分の装束色に田を染めて、やがてくる「稔り(みのり)」を約束して立ち去るのです。
しばしとてこそ立ち止まった西行の詩魂の霊魂が、いま芭蕉の目前で立ち去ったのです。
(2012年4月)
安田登 プロフィール
1956年生まれ。能楽師、ワキ方、下掛宝生流。公認ロルファー(米国のボディワーク、ロルフィングの専門家)。著作に『異界を旅する能』
『身体能力を高める「和の所作」』
『身体感覚で「論語」を読みなおす。』
『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。』
など多数ある。
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.