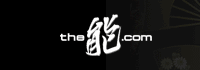 |
 |
 |
| > Top > ESSAY 安田登の「能を旅する」第2回 |
|
|
亡霊や精霊である“シテ”と 出会うところから始まります――。
連載「ワキから見る能の世界」では、
舞台でワキ方として活躍されている安田登氏に、
旅人・“ワキ”の目線から見た、能の世界を語っていただきます。
名所旧跡とワキ、そして……
前回は、夢幻能の構造と、能はワキの旅から始まることが多いというお話をしました。
しかし、能といえばシテです。ワキという言葉は聞きなれない。聞きなれないから勝手に「ワキ=脇役」だと思ってしまう。そこで「ワキ」については次回にもう少し詳しくお話をすることにしましょう、ということで終わりました。
ワキとは何か、そしてワキはどうして名所旧跡で幽霊に会うことができるのか、さらにワキが幽霊に会うにはどのような意味があるのか、そういうことを今回は見ていきましょう。
 |
© Paylessimages - Fotolia.com |
まず最初に「ワキ=脇役」という風に思っている方、一度それを忘れてください。能ができた当時、ワキには脇役という意味はありませんでした。
ワキというのは「分く(分ける)」というコトバからきています。ですからワキというのは「分く人」すなわち「分からせる人」であり、「分ける人」なのです。
では、何を分からせ、何を分けるのかというと、まずは「シテの姿」を観客に分からせる、ここからワキの仕事は始まります。
私たちもワキと同じく名所旧跡に行くことはあります。が、ほとんどの人はワキのような体験はしない。里人に話しかけられて、その里人が「実は昔語りの主人公の化身=幽霊だった」なんてことはない。
しかし、そこに化身はいる。
確かにいるのですが、それを私たちが見ることができないだけなのです。その見えないシテの姿を観客に見せる、すなわち観客に分からせるのがワキの第一の仕事です。
ワキは不可視のシテを分から(ワキ)せます。
ワキである旅人は問いかけます
さて、ワキの第二の仕事、今度はシテに向かいます。
シテ、すなわち幽霊がなぜこの世に現れるのかというと、それは何か思い残したことがあるからです。それを晴らすために何度もこの世に現れる。
そんなシテに、ワキである旅人は問いかけます。
が、本当に悩んだりしているときに「どうしたの」と聞かれて、「実はね」と理路整然と話せる人はほとんどいない。すっきり話せれば、思いもスッキリする。だいたいがぐちゃぐちゃです。
そんなぐちゃくちゃな「思い」を、快刀乱麻を断つがごとくに「分けて」スッキリするお手伝いをするのもワキの役割なのです。
これをワキは、ただ「問う」ということによって実現します。この問いかけ、現代のカウンセリングにも似ているのですが、その話をしていくと話がぐちゃぐちゃになってしまって、それこそワキの登場を願わなければならなくなるので、ここでは「ワキは問うことによって、ぐちゃぐちゃになっているシテの思いをスッキリさせる」ということだけを書いて、話を先に進めることにしましょう。
自分の思いが明確になったシテは、あとはもう勝手に語り始めます。そうなったらもうワキは口を挟まない方がいい。舞台のワキ座と呼ばれる定位置でつくねんと座し、シテの語りをただ聞き、思いの発露のごとき「舞」をただただ静かに見つめます。
この役割が大切なのですが、お客さんからはかなりヒマそうに見えるらしく江戸時代の川柳に…
「ワキ僧はたばこ盆でも欲しく見え」
…なんていうのがあります。「江戸時代からそんなにヒマそうに見えたんだ」ということのわかる句ですが、この姿からワキ=脇役というのが生まれたという説もあります。
 |
© James Hannibal - Fotolia.com |
さて、ではなぜ私たちには見えない幽霊が、ワキだけに見えるのか。
ワキとは本来は着物のワキの部分を指します。着物はこのワキを境にして前身頃と後身頃とに分かれます。前と後ろを分ける部分としてのワキです。
かりに私たち生者の住む世界が前身頃だとすれば、幽霊たちの住む世界は後身頃。あ、ちなみに日本古来の考えではカミ(神)と幽霊は同じ世界=常世(とこよ)に住んでいます。これについてはいつかお話しましょう。
娑婆世界の住人である私たちと、常世の国の住人である神霊たちは、紙の表面と裏面にいるようなもので、ふつうならば会うことはありません。が、ワキはこの世でもあの世でもない、その境界の世界、すなわち「ワキ世界」の住人であるから、ふとあちらの世界の住人である幽霊や神霊と出会ってしまうのです。
境界に生きるマージナル・マン、それがワキなのです。
真っ暗闇の「人生の深淵」を覗いてしまう
となると次に気になるのは、なぜワキは人間なのに「ワキ世界」の住人になったのか、ということです。
最初に結論。彼は「欠落した人」だからです。ぶっちゃけていうと人生を落伍したか、あるいはイヤになってしまった人です。
能のワキは無名の人が多いのですが、それもその一証。「諸国一見(諸国の旧跡や寺社を一見する)の僧」や「一所不住(住処を定めない)僧」が定番。彼らには名もないし、住所もない。住所不定、氏名未詳なんていうと、いまだとちょっとアブナイ人になってしまいますが、そう、そんな人がワキなのです。
そんな中で名前がわかる数少ないワキに「蓮生(れんせい・れんしょう)法師」という旅の僧がいます。実は蓮生、もとは武士。源平合戦において源氏方についていた〈勝てば官軍〉の、しかも超エリート武士「熊谷次郎直実(以下、熊谷)」でした。
彼の人生は順風満帆、出世街道まっしぐら!
が、そんな彼があるとき急に、真っ暗闇の「人生の深淵」を覗くことになるのです。それは少年武将、平敦盛(あつもり)を討たなければならない状況に追い込まれたからです。
その日の戦いも終わろうとする夕方、逃げ遅れたひとりの平家の武将がいた。熊谷は馬、近寄せて、むずと組み、武将を馬から落とす。兜を取って首を取ろうとすると、まだ少年。息子と同じ年頃です。
「ちょうど今朝、息子が怪我をした。それだけでも親である自分は心を痛める。もしこの子が死んだら親はどう思うか」
熊谷は彼を助けようとするのですが、後ろを見ると味方が五十騎ほどでやってくる。このまま逃がしても彼らに討たれる。「それならば自分が討って後生を弔おう」と泣く泣く首を掻き切るのです。
それで彼は出家をします(史実はいろいろあるようですが…)。
出家といっても、いまの出家とはちょっとわけが違います。ほとんど死に近い。特に熊谷が帰依したのは日本で最初の「日本人の・日本人による・日本人のための新興宗教」である浄土宗の開祖、法然上人です。熊谷は、この世の栄華や出世、楽しみや喜びはもう一切関係ない。その一生を衆生済度に捧げようと決断をするのです。
今でいえば末は次官か大臣かと言われていた超エリート官僚が、そのキャリアをすべて捨てて、無名のホームレス・ボランティアになるようなものです。
彼の人生は〈限りなく「無」(リミット・ゼロ)〉に近づく。が、それでも生きている。そうなったとき彼は、この世とあの世との境にいる「ワキ」になることができるのです。
おっと、ここで所定の字数になってしまいました。「ワキが幽霊に会うにはどのような意味があるのか」については、ひとつの旅が終わってからお話することにしましょう。
(2011年12月)
安田登 プロフィール
1956年生まれ。能楽師、ワキ方、下掛宝生流。公認ロルファー(米国のボディワーク、ロルフィングの専門家)。著作に『異界を旅する能』
『身体能力を高める「和の所作」』
『身体感覚で「論語」を読みなおす。』
『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。』
など多数ある。
|免責事項|お問い合わせ|リンク許可|運営会社|
Copyright©
2026
CaliberCast, Ltd All right reserved.